.jpeg)
なんか調子が悪い、もっとうまくなりたい、
そのためにアンブシュアを変えたら逆にもっと調子を崩してしまった・・・
そんな経験をお持ちの方も少なくないのでは?
ここまでお話してきたとおりアンブシュアは結果として出来上がるものであって、アンブシュアの形からアプローチしてもあまり意味はありません。
たぶん合奏終わったら元通りです。または常にアンブシュアの調整を意識し続けて音楽表現に集中できないような状況になります。
では、一度崩してしまった調子を再び上向かせるにはどうしたら良いのでしょうか。
それには、呼吸・発声・口の中の形から順番に整え直してあげることが非常に効果的です。
呼吸や発声から順番に整えていくと自然と良きところに収まるものです。
また、そうなった時には息の流れで歌を歌うような吹き方が出来上がり、アンブシュアなんか意識せずに音楽表現に集中できるようになります。
「きみはアンブシュアが良くないから、こういう当て方に直しなさい」
そんな指導を真に受けて全く吹けなり一年間の努力ののち、楽器から離れた人がいました。中学生のころからコンチェルトを演奏していたような人です。
その人は、去年また楽器が吹きたいとレッスンに訪れ、整え直すことで再び楽器を演奏することができるようになりました。
そして自然と現れたアンブシュアは「直しなさい」といわれる前の下に偏った当て方だったのです。
顔や声が違うように吹き方の見た目は人それぞれ。
身体の仕組みは同じなのだから整え方は共通です。

-177x104.jpeg)
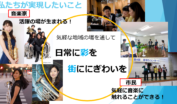

-1.png)
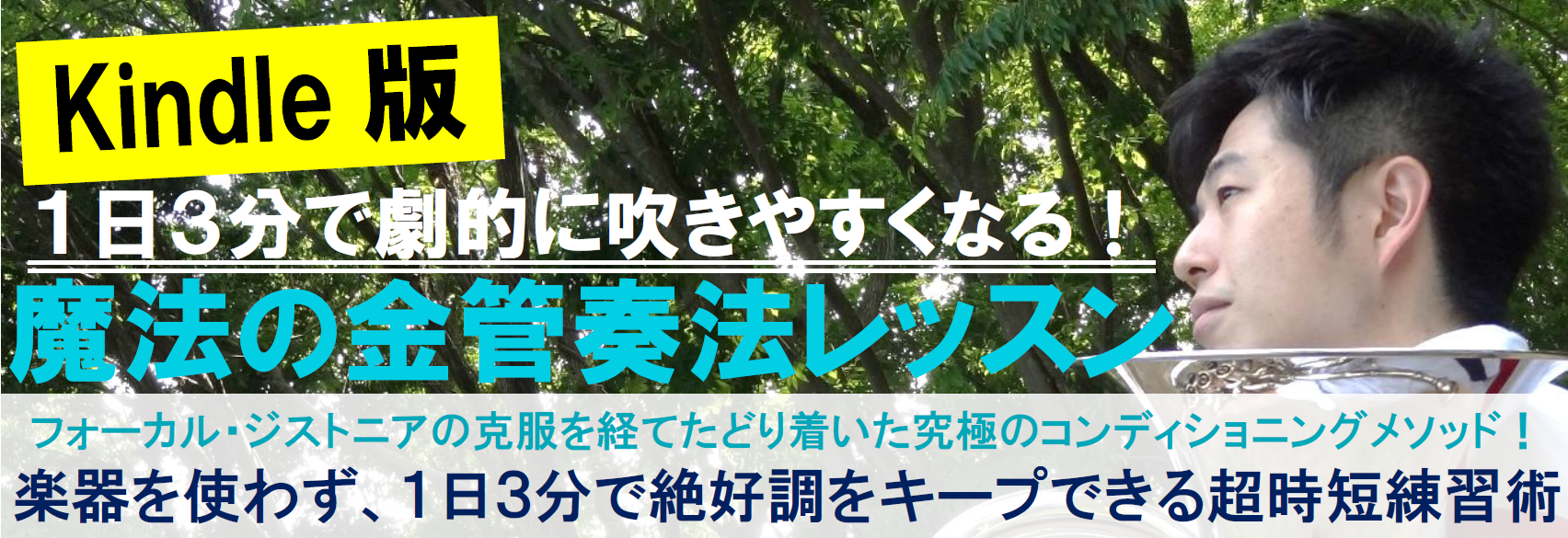
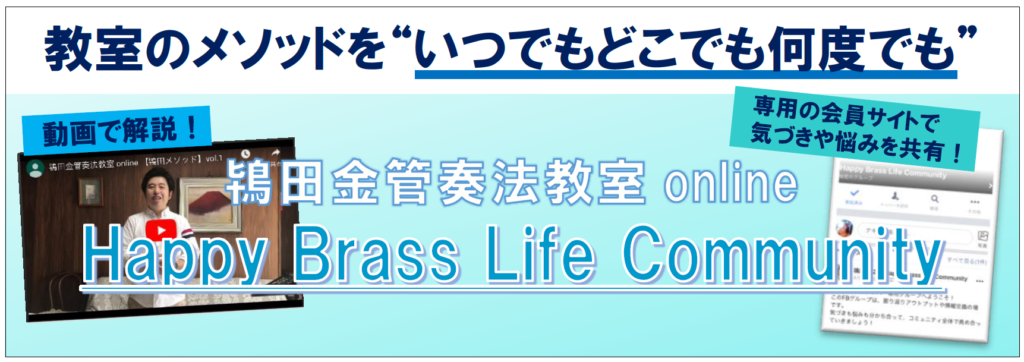
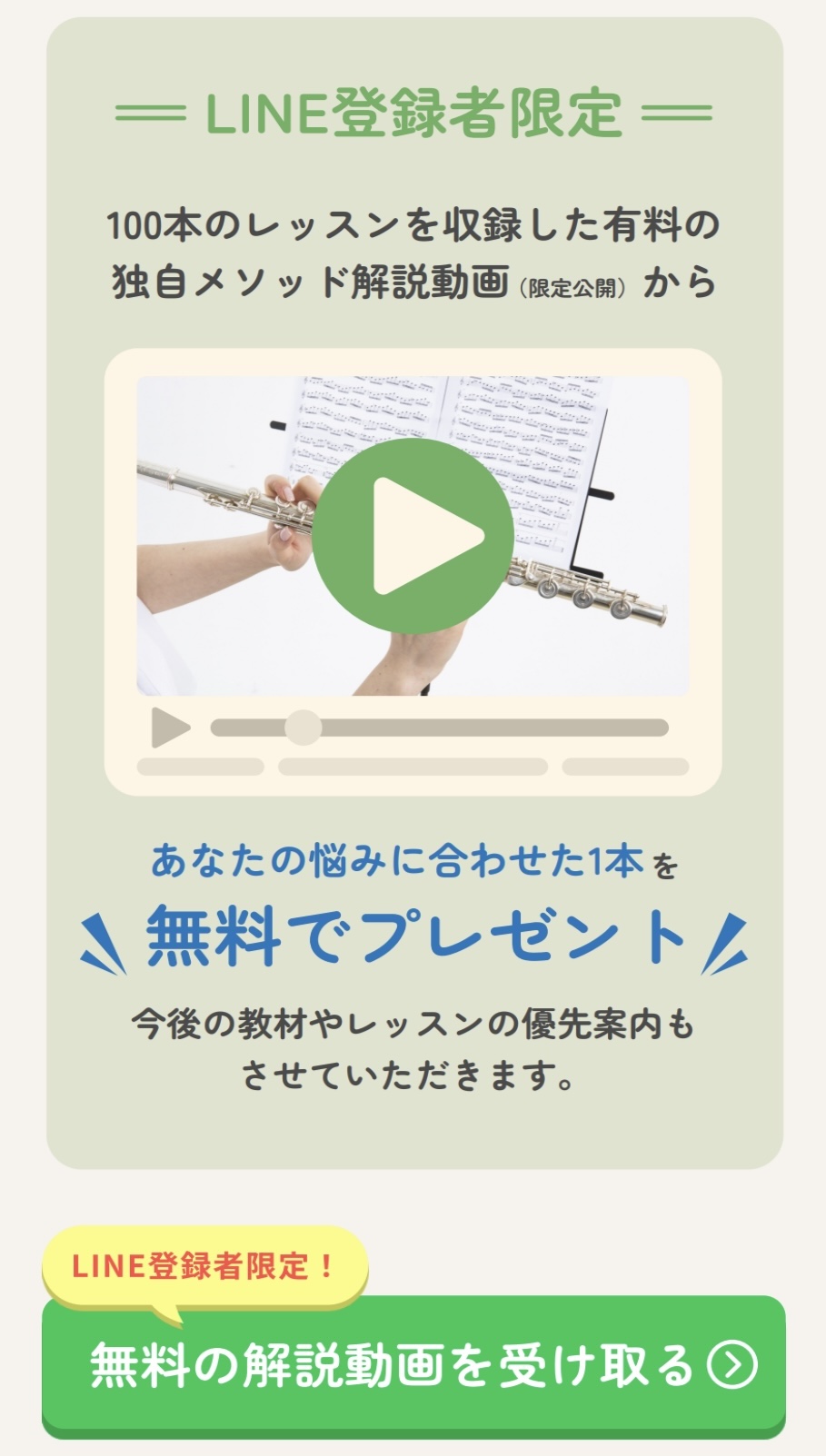
-181x181.jpeg)
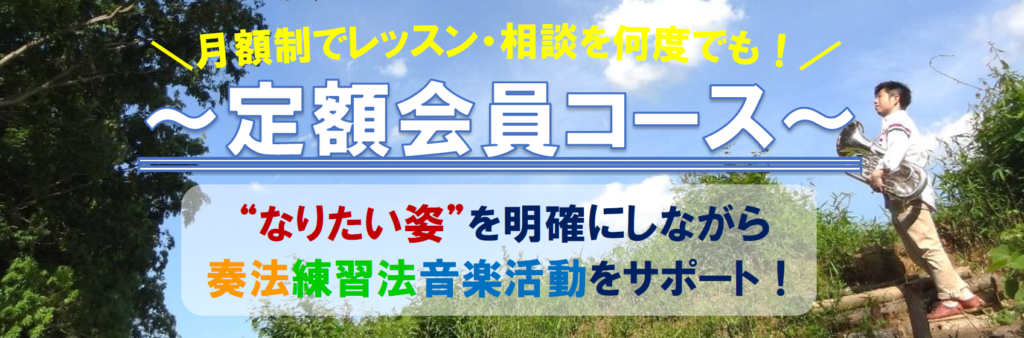

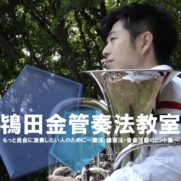



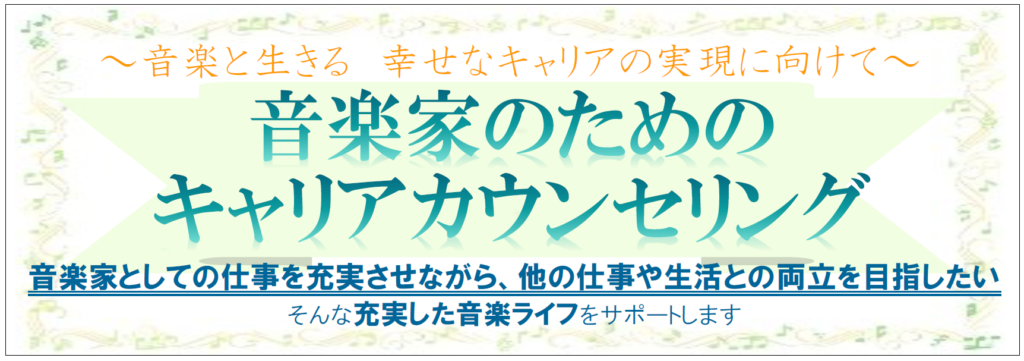
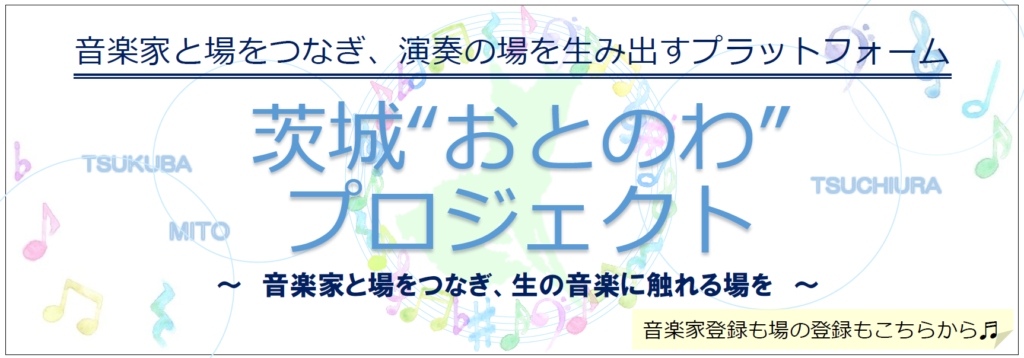
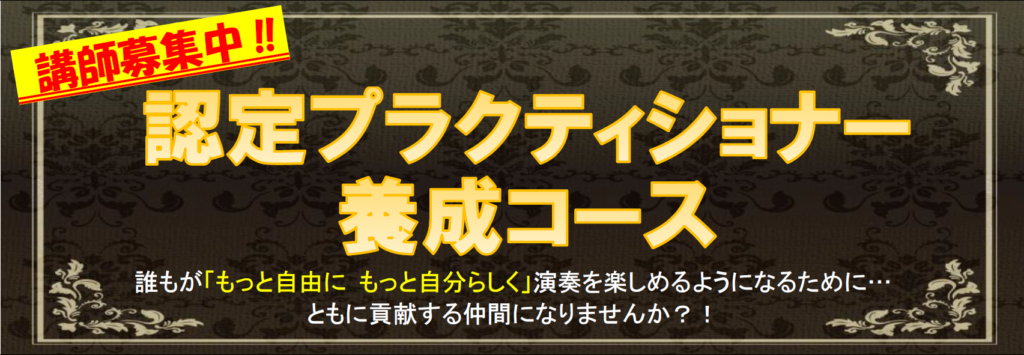

この記事へのコメントはありません。