.jpeg)
「息のスピードが遅い」って言われたことありますか?
僕も言われたことあるし、今の立場ではよく生徒に言います。
何故かというと息のスピードで解決できることがものすごくたくさんあるからです。
他の記事でも解説しているとおり、金管楽器の発音の仕組みは唇の振動音の共鳴ではありません。
唇の振動は息と楽器の共同作業によって結果的に引き起こされるものなので、主役は息なのです。
このスピードが足りないと、アンブシュアにたよって半ば強制的に振動を引きおこさなくてはならなくなります。
音やアンブシュアは息のスピードで支えてあげるものなのです。
前置きが長くなりましたが、ではその息のスピードとやらはどうやって作り出すものなのか。
①息を吸うスピード
吸ったように履くのが一番自然なので、まずは息を吸うスピードを上げることがとても大切。
実はこれだけでかなりの方が改善します。
ふわっと吸うとどうしても安定しないし、合奏や合唱では最初の一音のアタックや響きが揃いにくい。
同じスピード感でブレスが取れるとそれだけでたくさんのことが解決します。
②息を吐くスピード
吸うスピードがきちんとあれば吐くスピードについてはほとんど考える必要はありません。
例えば強烈なフォルテが欲しい時など、吐く息のサポートが足りないなと感じる時には、おへその少し下あたりに丹田と呼ばれる場所を意識すると良いと思います。
丹田というのは筋肉ではないのでなかなか意識しづらいのですが、おへその少し下あたりを指で押しながら咳払いをすると前に押し出すような動きを感じることができます。
この動きを利用すると息にパワーが生まれ、息のスピードを生み出すことができます。

-177x104.jpeg)


-1.png)
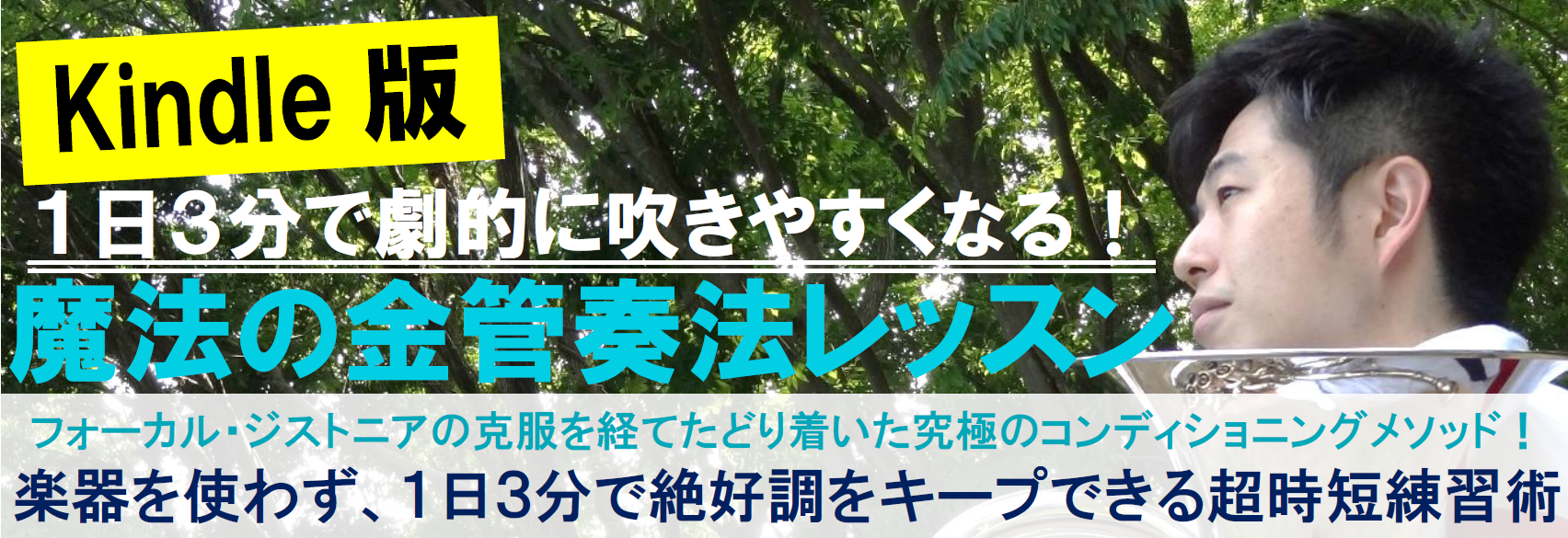
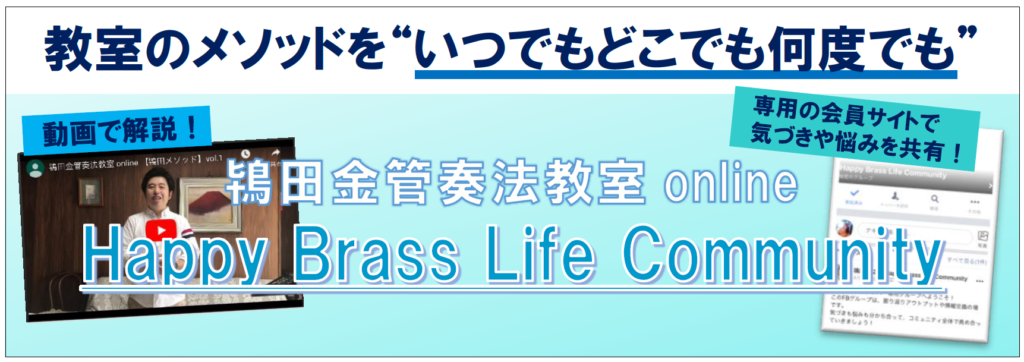
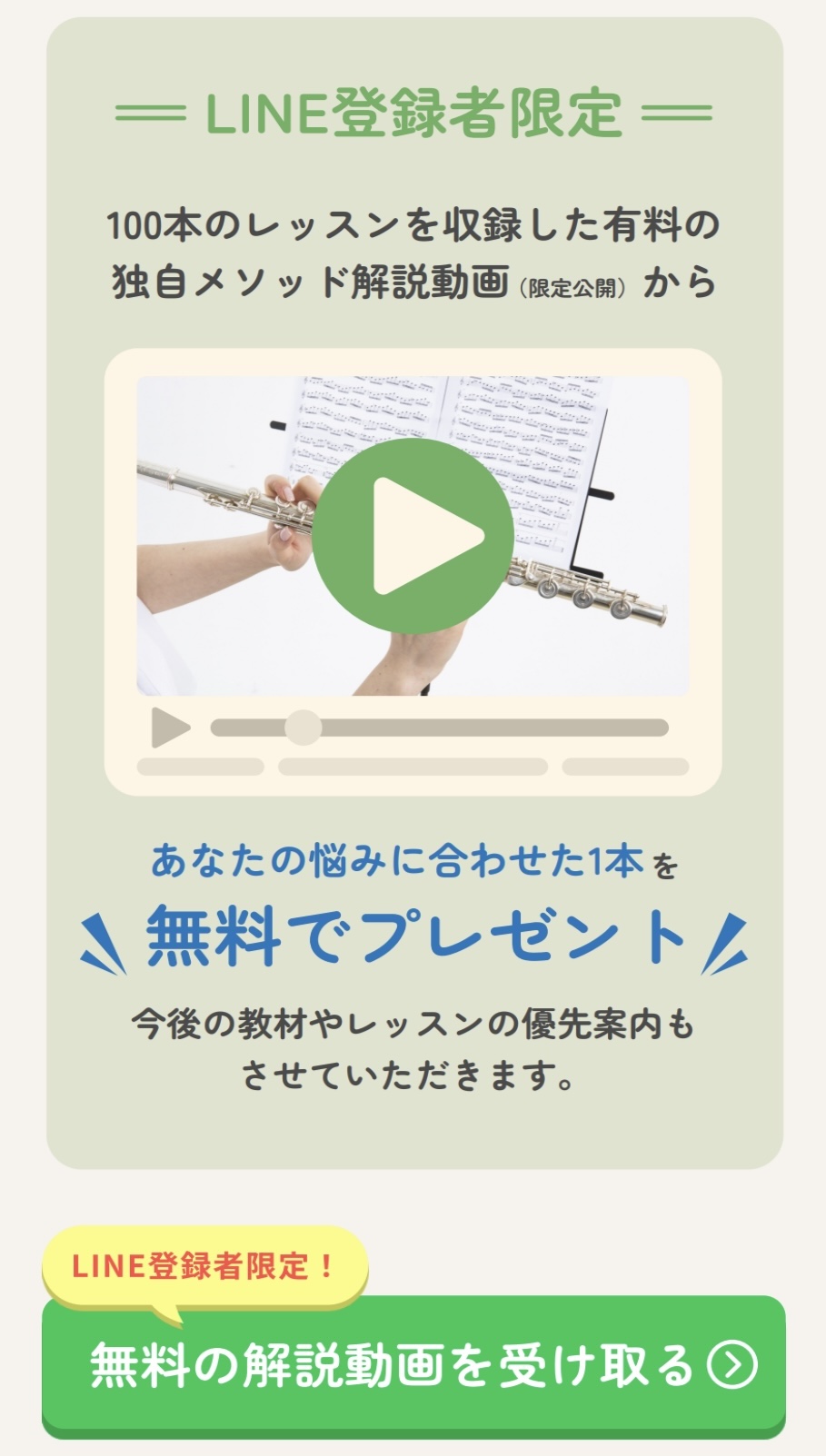
-181x181.jpeg)
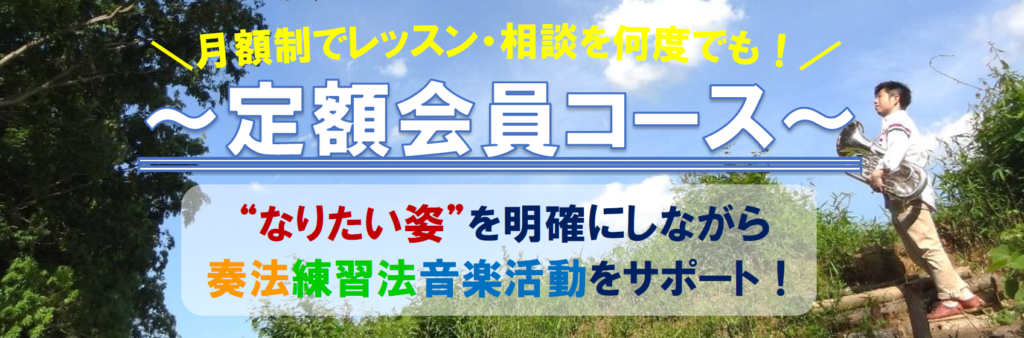

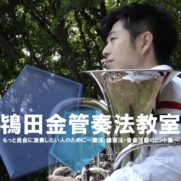



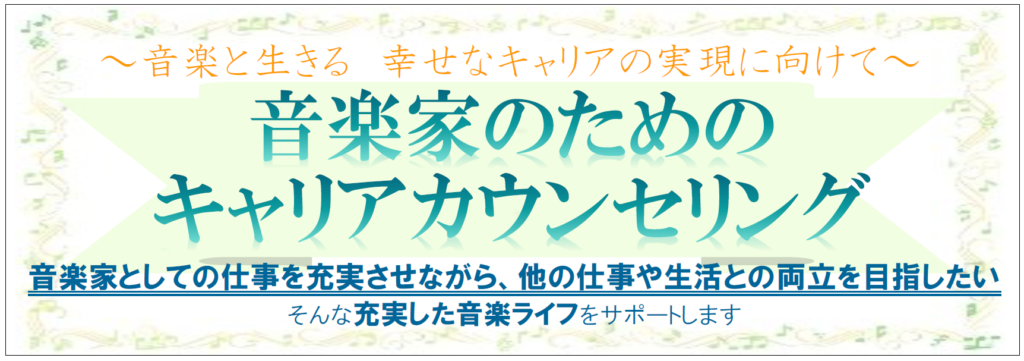
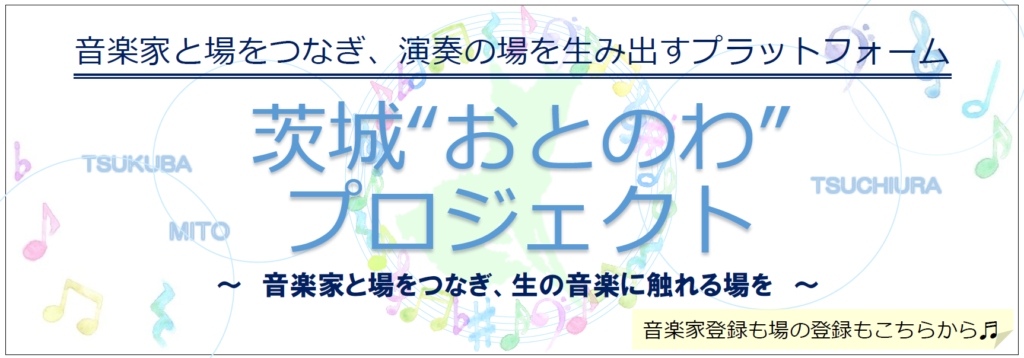
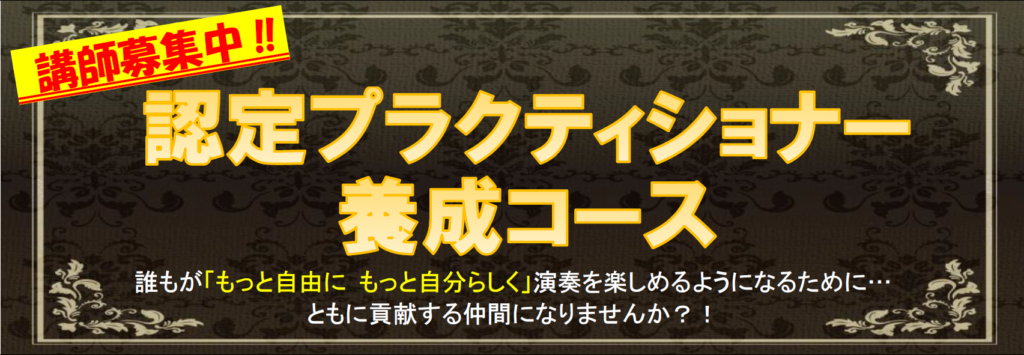

この記事へのコメントはありません。