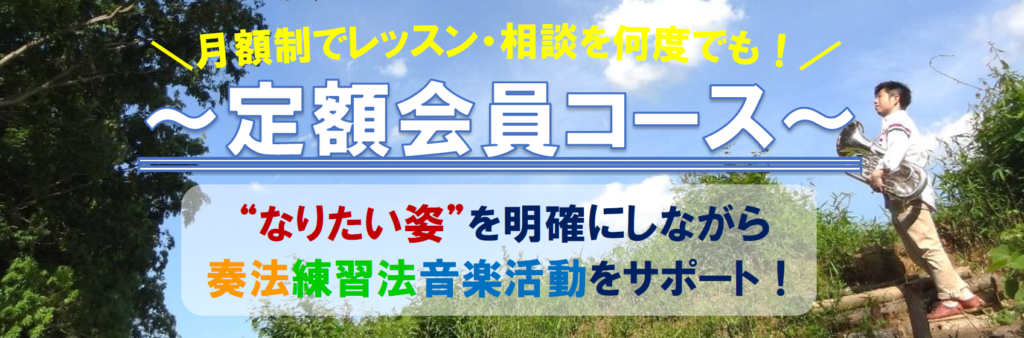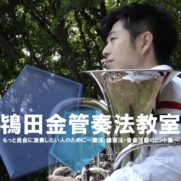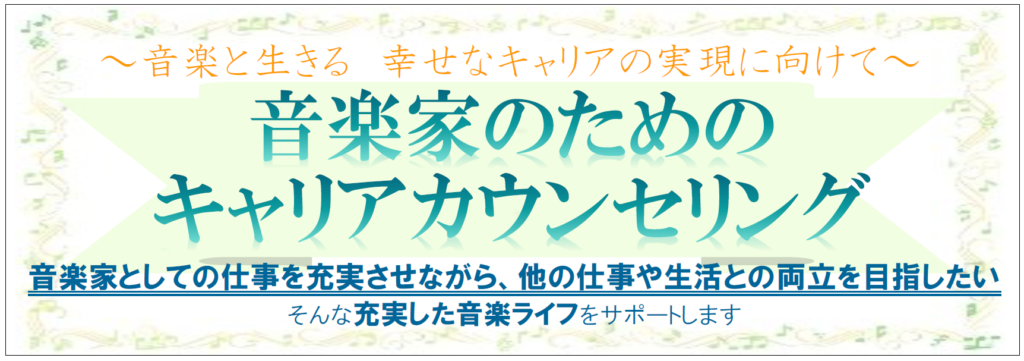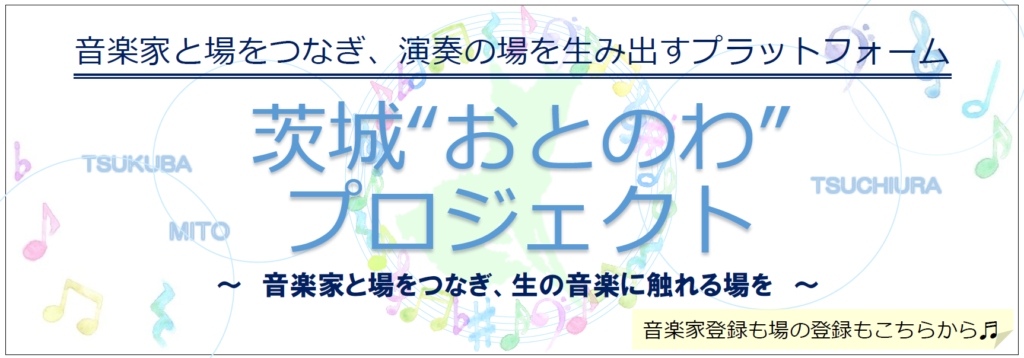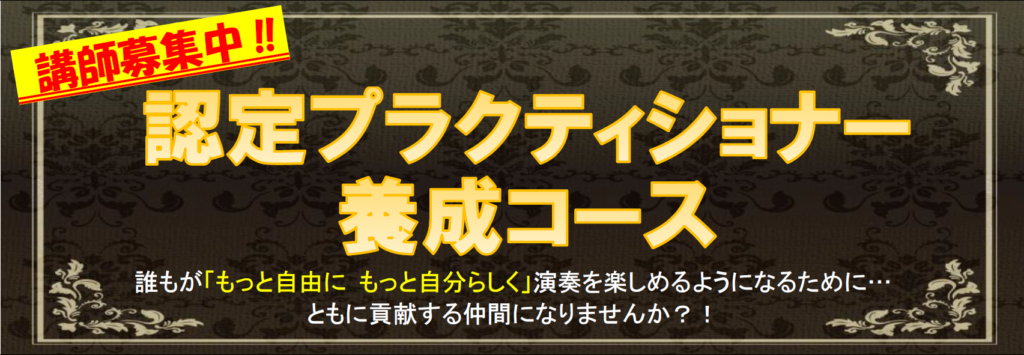.jpeg)
楽器が吹きづらくなってしまって、純粋に音楽表現に集中することができなくなってしまう。
そんな経験は誰しもあるものじゃないかなと思います。
そして、
アンブシュアが悪いからだとか
呼吸が浅いからだとか
姿勢が悪いからだという話になってくる。
そして、その部分に何らかの変更を加える。
そして、もっとわけがわからなくなる。
かといって、「じゃあ戻せばいいじゃん」で戻るほど簡単ではなかったりする。
なぜか戻したはずが戻らない…
さあ奏法の迷宮へようこそ!笑
今回はこういうときの対処法まとめていきます!
♫ 部分的なアプローチではなくて…
どこか一部だけ変えると噛み合わなくなりやすい。
例えばアンブシュアが悪いからといってアンブシュアの見た目や当て方だけ変えていくと、極端な場合全然吹けなくなってしまったりすることが結構あります。
ごく近しい人で、アンブシュアとマウスピースの当て方を「直されて」吹けなくなってしまい、1年踏ん張ったのちに楽器から離れた人がいました。
その人は、最近になってまた楽器を再開したくなって僕のところに来てくれました。
ずーっと心に引っかかっていたようで、自然に吹けるようになって人生変わったと言ってくれました。
また、こんなこともありました。
大学院時代にこのメソッドを論文にまとめていた頃、金管バンドのコーチをしていた後輩から電話がかかってきて…
「先輩大変です!コルネットパートの音色が良くないのはアンブシュアのせいだから直しておいて!と言われたから直したんです。そしたら…14人中10人が音も出なくなってしまいました!どうしましょう?!」
と…
3週間ほどお邪魔して、上手く軌道修正することができました。
アンブシュアだけいじるからおかしくなるのです。
呼吸から順番に整えて持って行ってあげると、アンブシュアの形は自然といい感じに整ってきます!
♫ いよいよ本題に入ります…
整えたあとは、
今までの癖と新しい癖が共存している状態なのです。
この状態から脱却するには、
段々と新しい癖が育っていくように習慣づけてあげることが大切です!
呼吸はこんな風に動く。
発声はこんな風にリンクする。
口の中はこんな感じ。
で、結果としてアンブシュアはこうなる。
と体に教えてあげる。
最初は意識的にやることで体が気付いてくれます。
それを段々と無意識にしていく。
反復によって無意識化していく。
そんな取り組みが大切です。
そのための練習法がルーティーンになっていると自然と無意識化することができる。
だからこそ、順番に整えることができる一連の練習法を持っているといいのです!
♫ まとめ
そんなわけで、今回は吹き方の変化や不調を乗り越えるための考え方を述べさせていただきました。
そのためのやり方は人それぞれ様々ですが、
吹き方の変化や不調を乗り越えるためにはこんな考え方がいいかなと思っています。
悩んでいる人が少しでもいい方向に進めますように!
鴇田 英之

-177x104.jpeg)

-1.png)
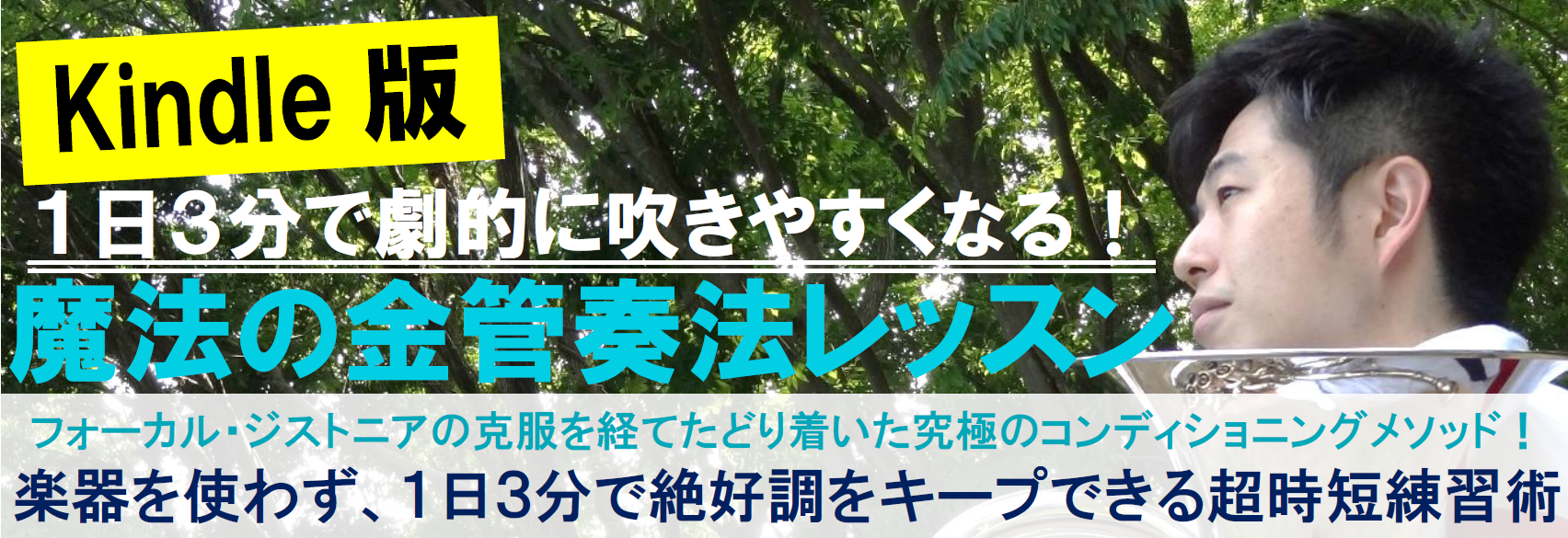
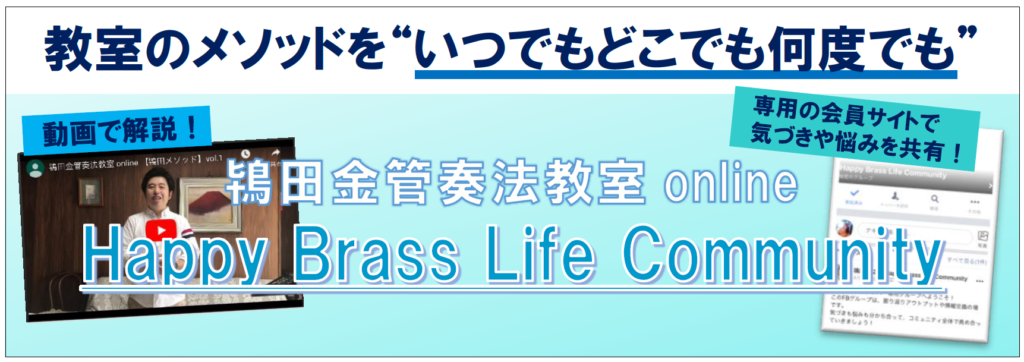
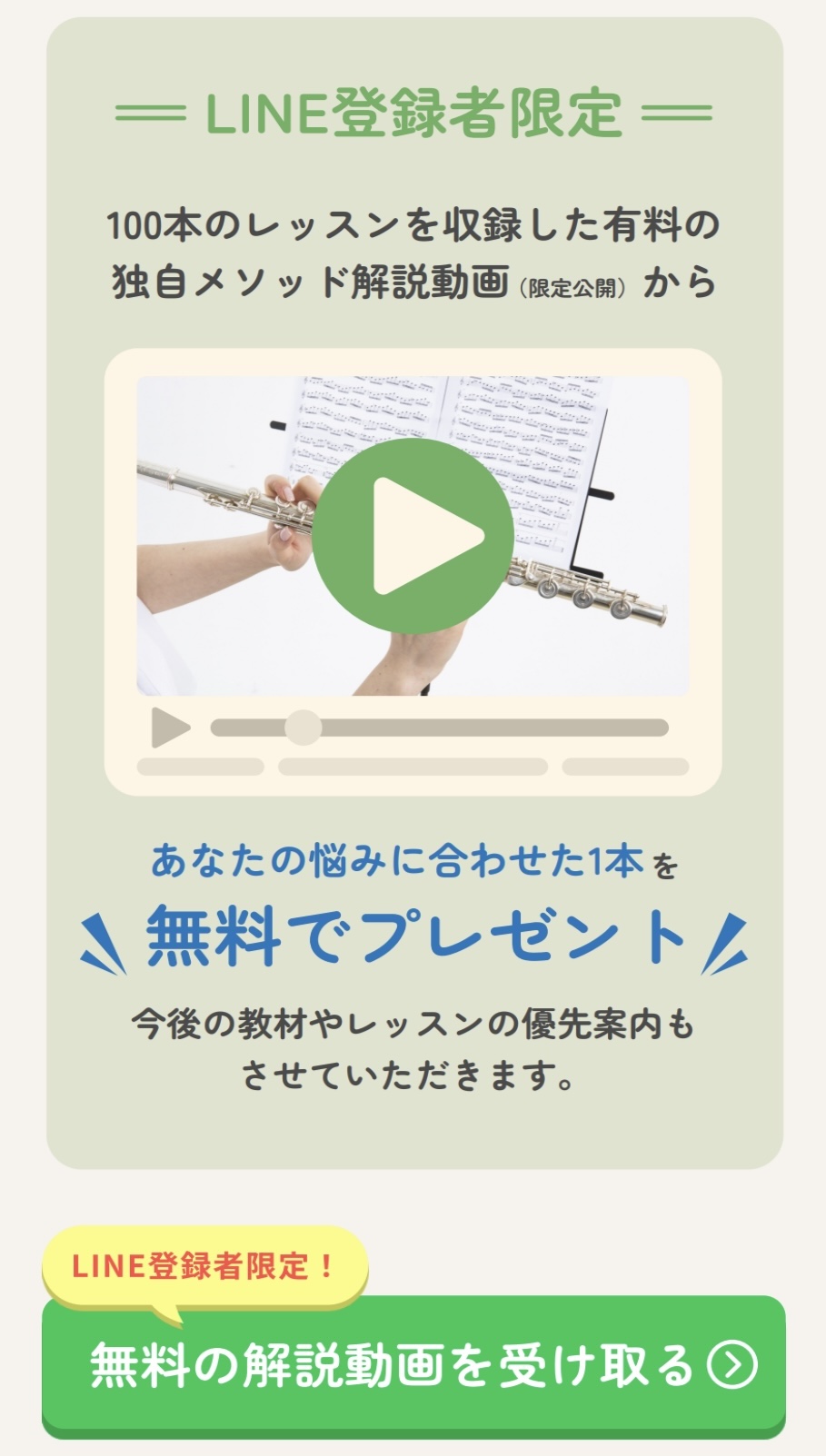
-181x181.jpeg)