.jpeg)
今日のレッスンでの会話から。
「トランペットの子で1年生の時にアンブシュアがだめだから直しなさいって言われてマウスピースの当て方を変えたら全然吹けなくなっちゃった子がいて、その子は結局クラにいきました。中学校では1st吹いてたのに…」
なんともつらいお話です・・・
アンブシュアの見た目なんて結果でしかないのだから、内側(呼吸や発声や発音原理の理解)を整えられるように練習して、結果として改善されるのが本当だと思う。
他にもアンブシュアを変えた生徒がいたようでその生徒もだんだんともとの吹き方に戻ってきていると。
そもそも変える目的ってなんなんでしょう?
変えた方が上手くなる気がするからですかね…
この話を聞かせてくれた生徒は、呼吸から順番に整えていって、今では吹き方が安定してきました。
初めて来たときには「アンブシュアが…」といっていました。角度を変えるなど工夫して吹いているようでしたが、順番に整えることで小細工は要らなくなり、普通に吹けるようになってきたとのこと。
やはりベースにあるのは呼吸と発声だと思います。
特に歌う経験があまりなかったようで、2回目のレッスンはしっかり発声をやりました。
その後で楽器を吹いたときは、「こんな楽に吹けた事ない」と驚いていました。
突き詰めればとってもシンプルなこと。
部分的なアプローチで上手くいかない事も、全体のつながりで捉えて整えていくと解決します。
それを知っているか知らないかの違いは大きい。
かくいう僕も相当な遠回りをしましたが…笑

-177x104.jpeg)


-1.png)
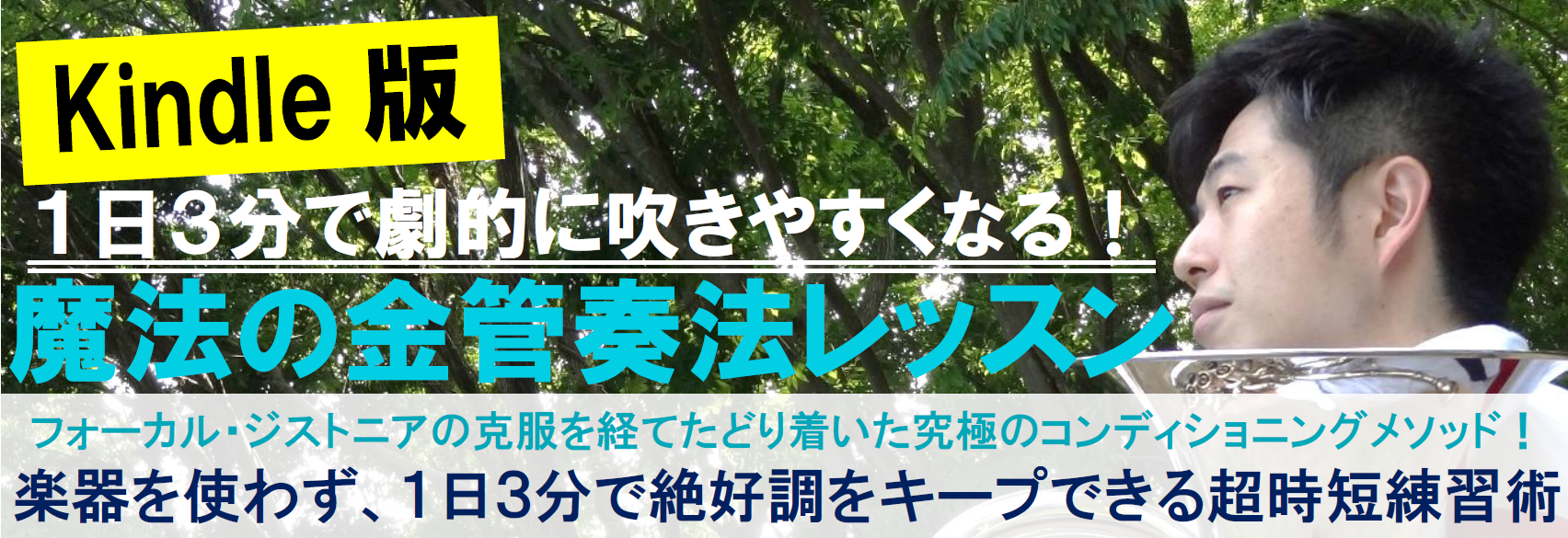
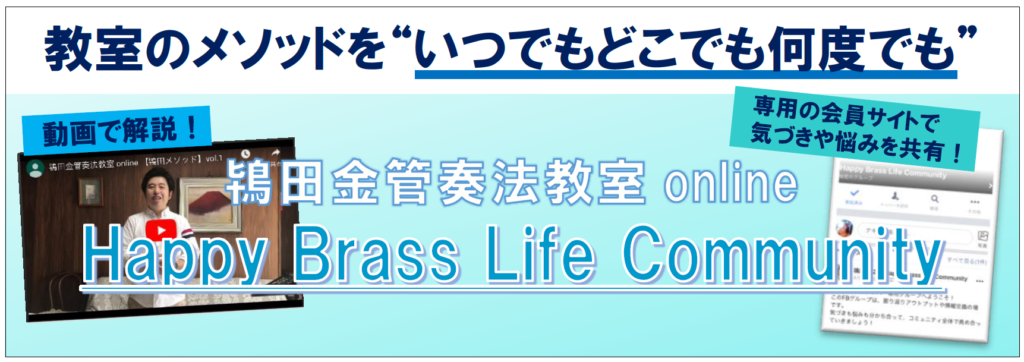
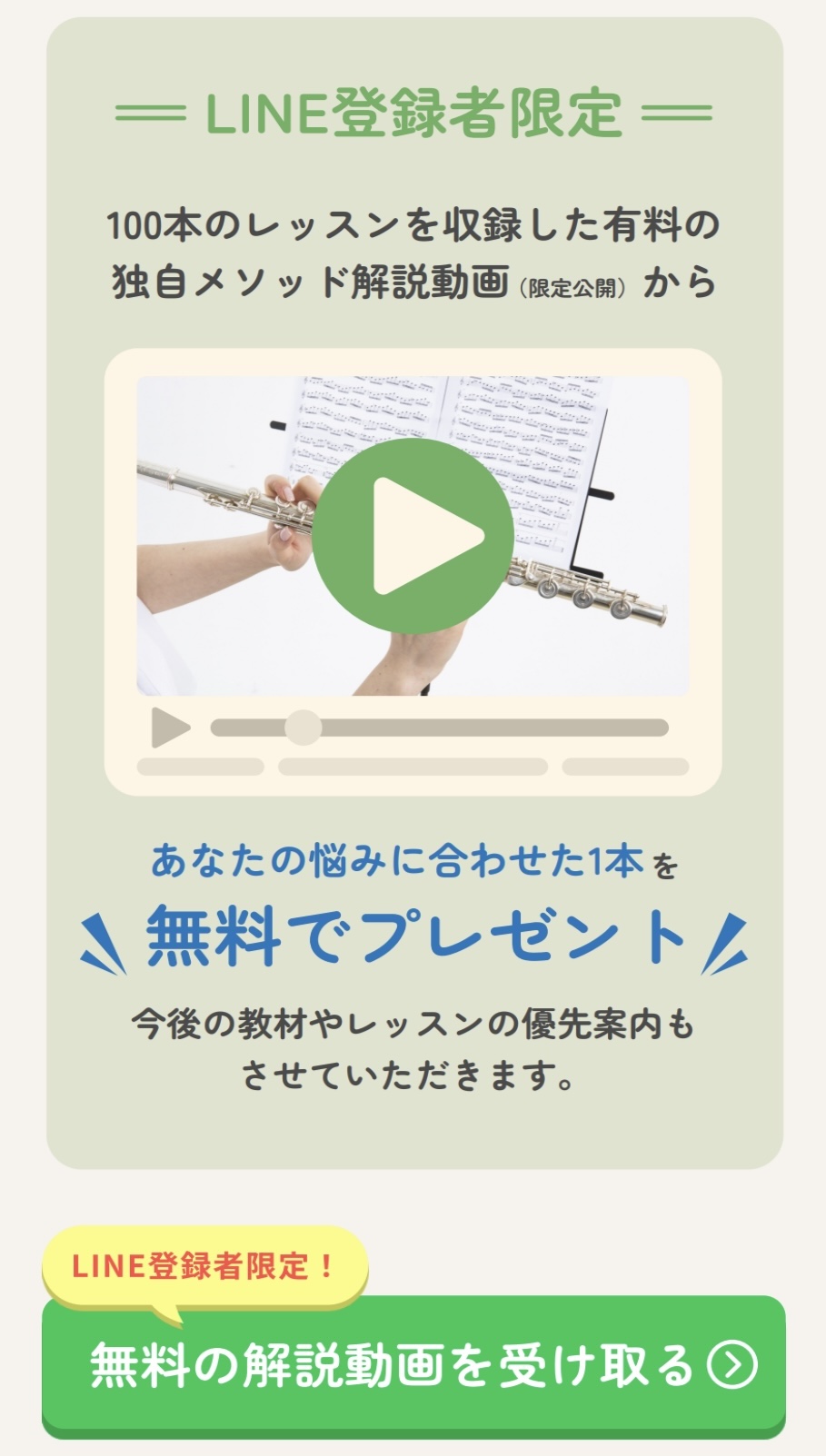
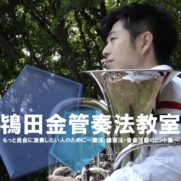
-181x181.jpeg)

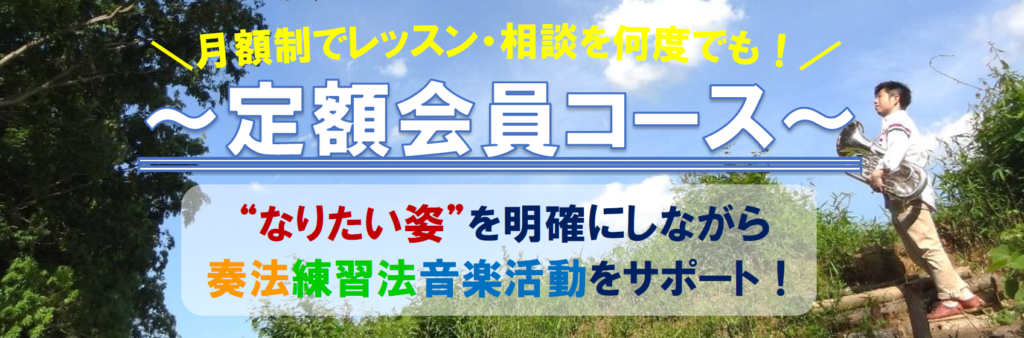




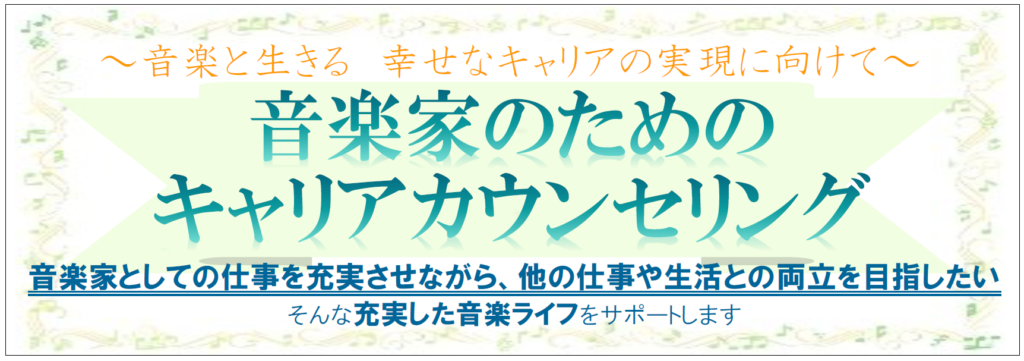
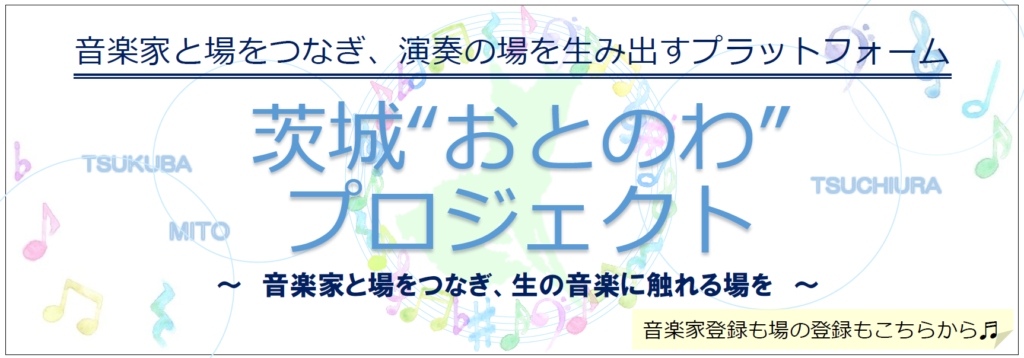
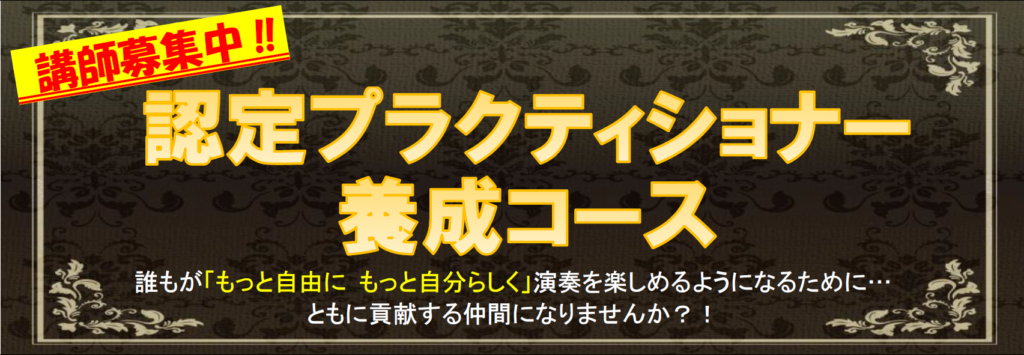

この記事へのコメントはありません。