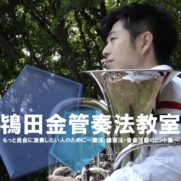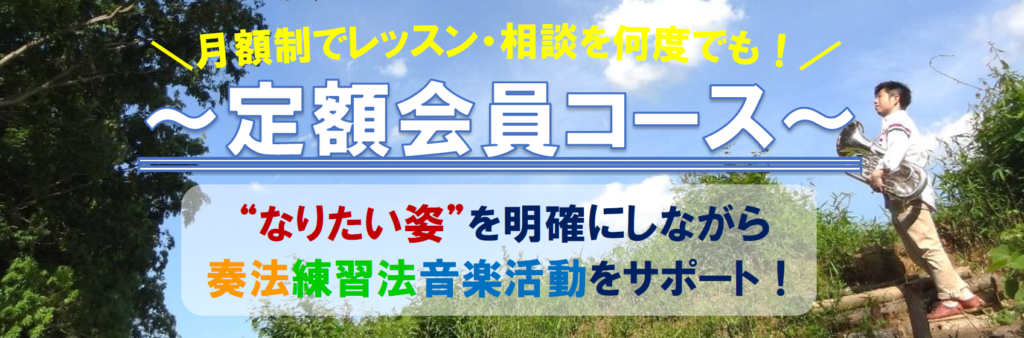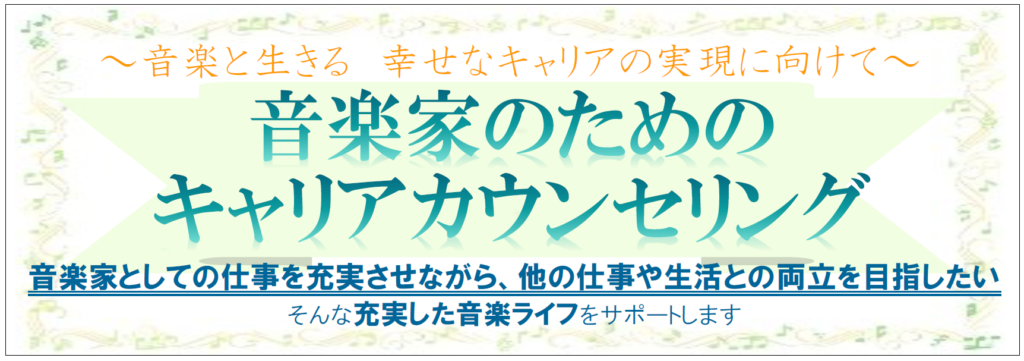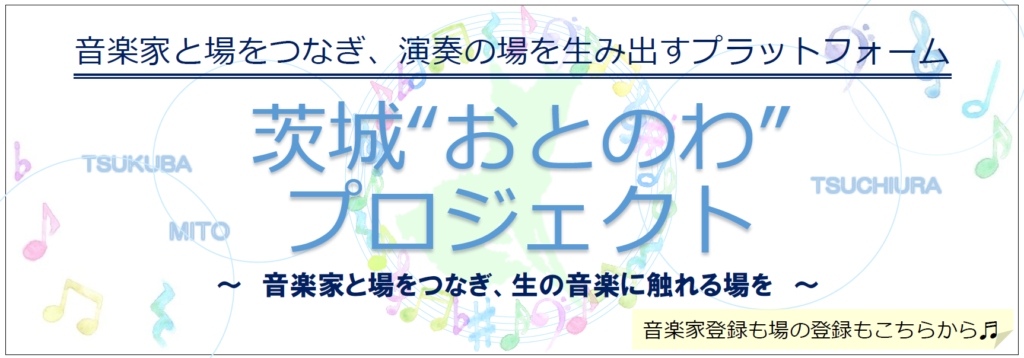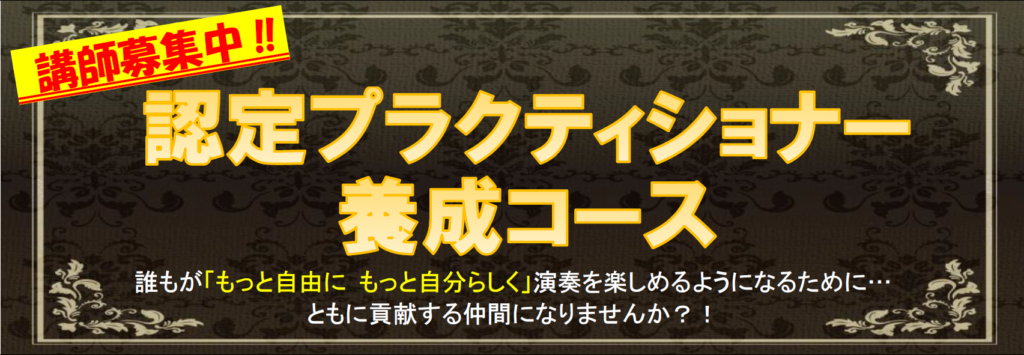.jpeg)
さて、昨日の文章の中で、フォーカル・ジストニアという言葉を使いましたが、この言葉(この病気)をご存知の方どれくらいいらっしゃるでしょう。
フォーカル・ジストニアとは、発症すると特定の動作をするときにだけ、例えば楽器を吹くときにだけ、自分の意思とは関係なく不要な力が入って思うように動かせなくなりますす。
(詳しく知りたい方は「どうして弾けなくなるの?音楽家のジストニアの正しい理解のために」という本がとても読みやすいので読んでみてください)
今ではある程度知名度のある病気になったようですが、この症状、周りの理解がないことが一番辛いのです。
なので、今日はジストニアについて少し書きたいと思います。
僕の場合は、2010年頃から中音域が発音できなくなり、やがてその症状は全音域に広がっていきました。
医師の診断によると、左の頬にある笑筋という筋肉に大元の原因があるとのことでした。自分では気がつきませんでしたが、左の頬の筋肉が勝手に収縮してしまうことで唇をうまく閉じることができなくなっていたようです。
そこで、その筋肉に麻酔を打った状態で練習する事で新しくアンブシュアを作り直すという方法で治療が進みました。
(決して怪しい病院ではありません。音楽家専門外来という科がある大学病院もあります)
ジストニアの治療は、”正しい動作を覚え直す”事で進んでいきます。
そのため、まずは勝手に不要な動きをしている笑筋の緊張を弱める必要があったのでしょう。
治療はうまくいき、唇は閉じられるようになりました。
しかし、楽器を吹く感覚は全く戻らず、8歳から吹いてきたこの楽器がまるで始めて触る楽器のように感じ、全く吹き方がわからなくなっていました。
症状は緩和したものの楽器を吹けるようにはならず、結局、修了演奏は懸命に音を出そうとしながら大ホールのステージで立ち尽くしているだけ…
と、こんな辛い時代がありました。
そういう病気があるということを周囲が理解しているだけで、当事者は救われます。
当の本人だって、病気のせいじゃなくて自分が下手くそなだけなんじゃないかと思っています。もし周りにあれ?そうかも…と思う人がいたらそっと寄り添ってあげてください。その人もきっとそのうち話し出しますから聞いてあげてくださいね。
また、そこから這い上がってこられたのは、奏法について勉強して、”正しい動作を覚え直す”ための練習法を編み出せたからです。
僕の場合は動作を覚え直すというより、正しい感覚を作り直すという感じかなと思います。
吹けなくなった直後は、マウスピースが半分くらいになったように感じ、アンブシュアもアパチュアも一回り小さくなるような不思議な感覚でした。
そこから、マウスピースがこのサイズだから使う筋肉はこっちの筋肉に変わって…などと最初はやっていたけれど、そんなことやってても本質的にはなんの解決にもなりません。
筋肉から意識を離すと元に戻ってしまって、とても音楽表現どころではなくなってしまうからです。
復帰するためにはうまく機能するアンブシュアが自然にできあがる練習方法が必要でした。
そこで得た練習方法をもとに、吹き方に悩む方がもっと自由に楽器を吹くことができるよう貢献していきたいと思います。

-177x104.jpeg)
-1.png)
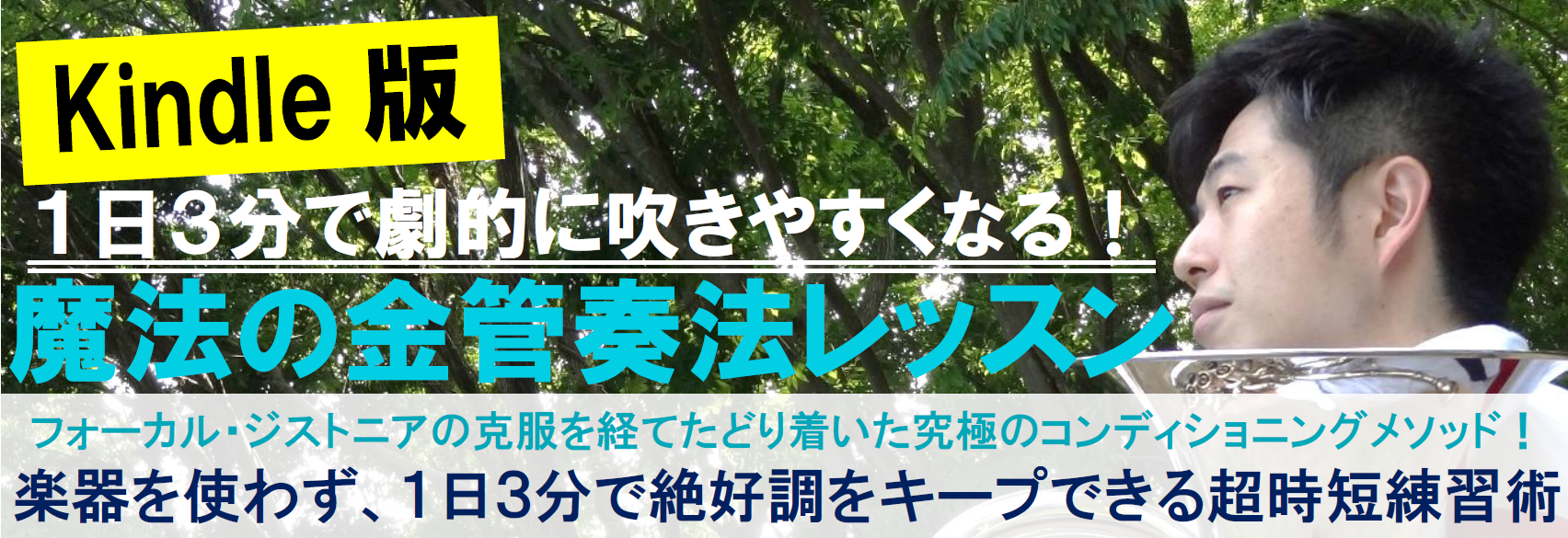
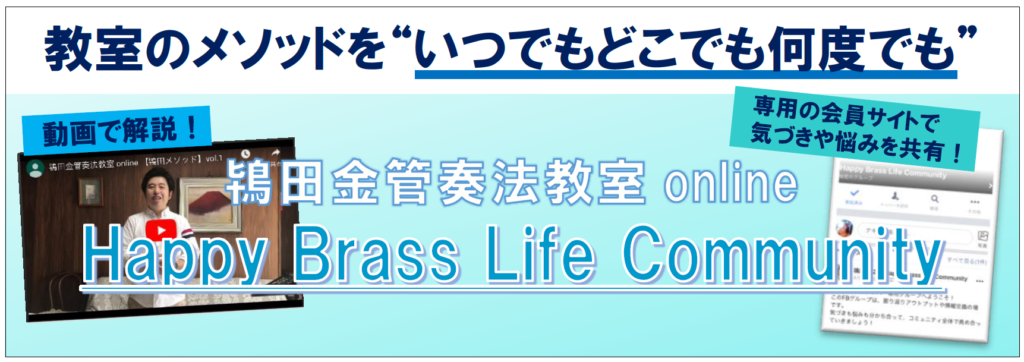
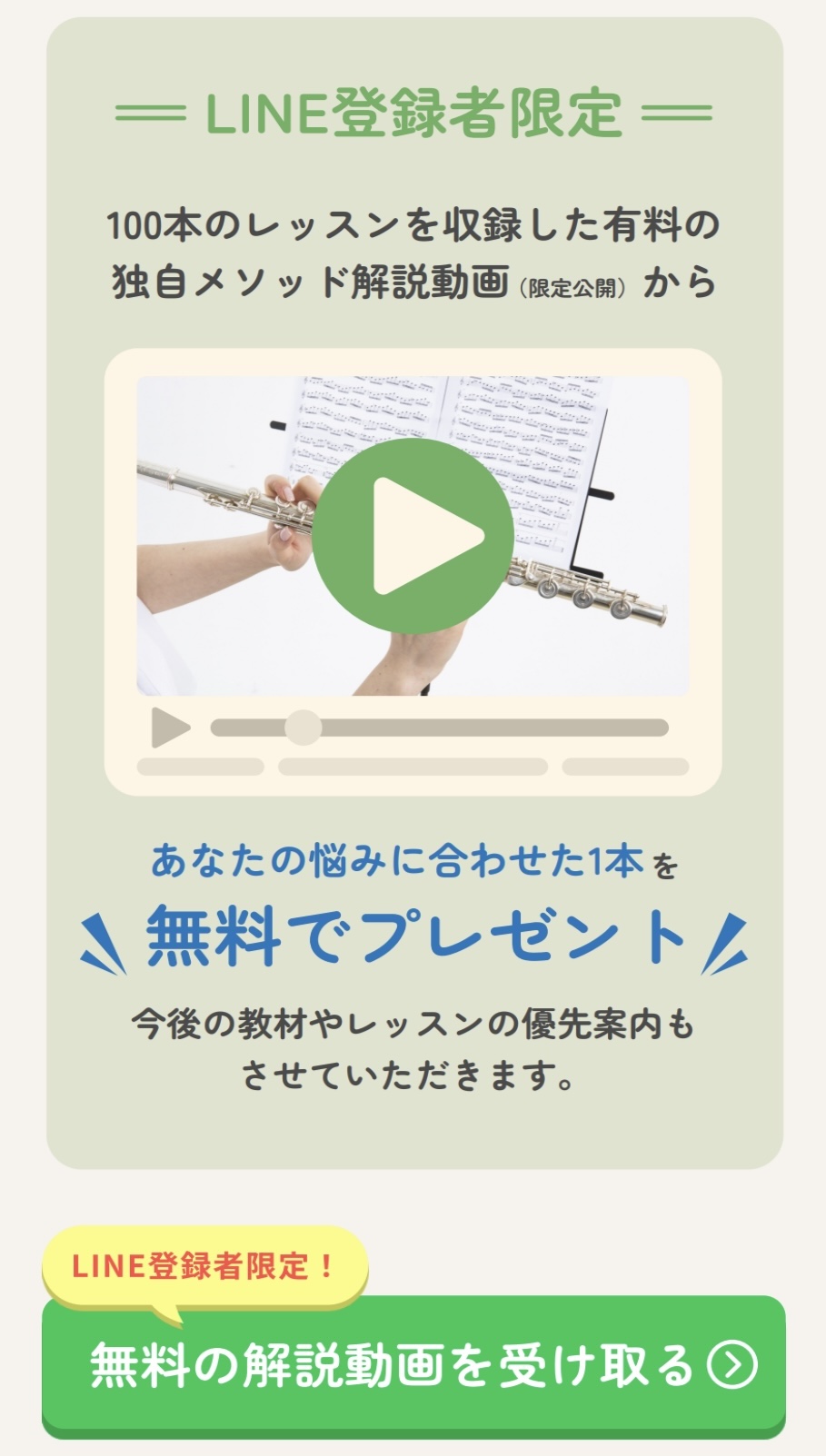
-181x181.jpeg)