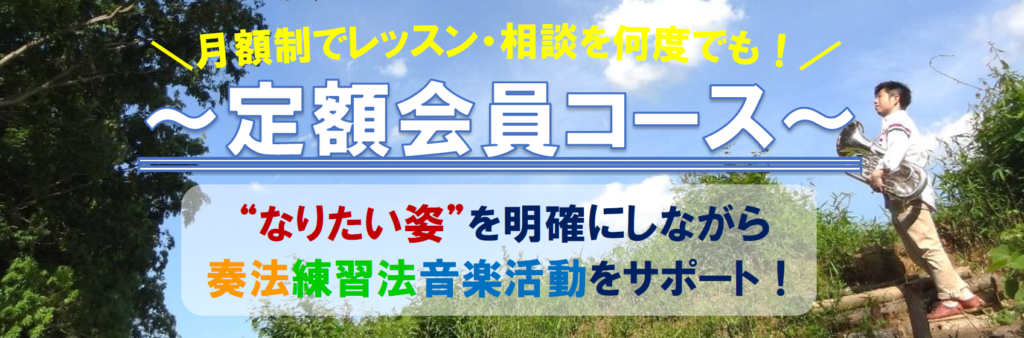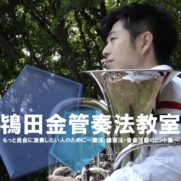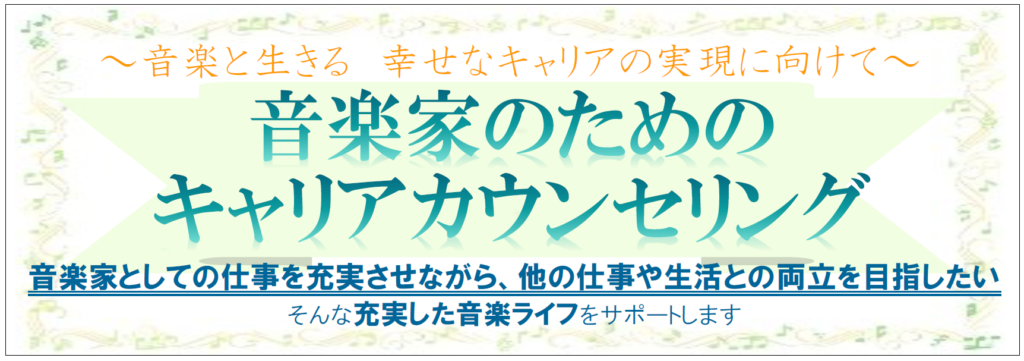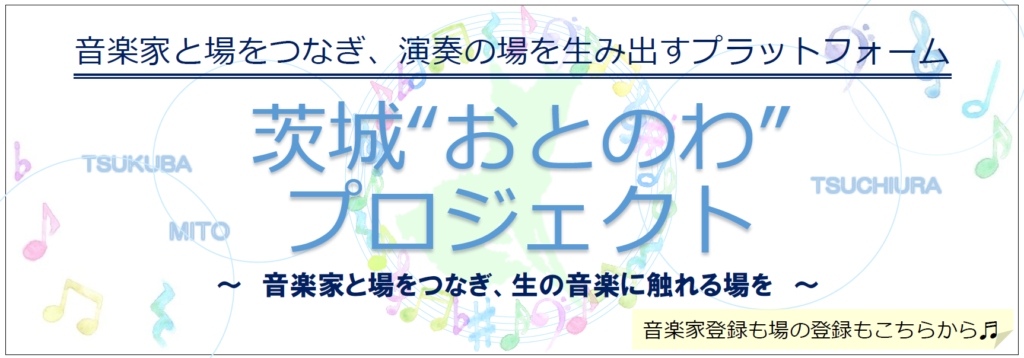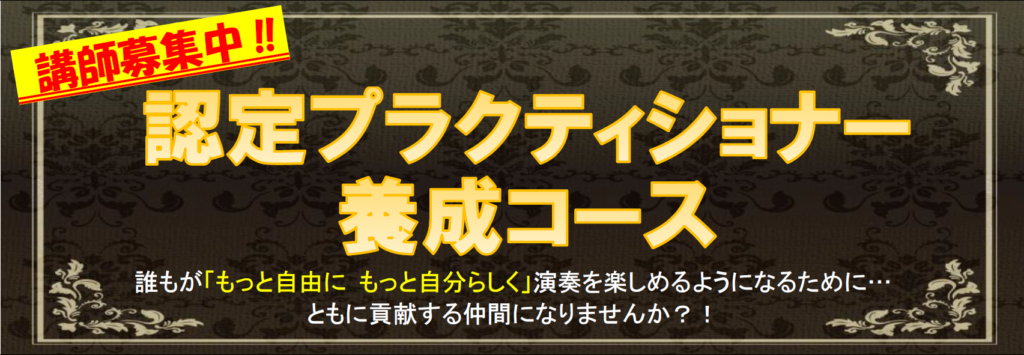.jpeg)
声の響かせ方を楽器の響かせ方とリンクさせるとものすごく吹きやすくなります。
以前、“声の響かせ方を自動的に楽器の演奏に生かせるようになる発声練習“について書きましたが、今日はさらにその一歩先のお話です。
1.マスケラとは。
「マスケラ」という言葉、ご存知でしょうか?
声楽の方ならご存知の方も多い言葉だと思いますが、金管楽器だとあまり馴染みのない言葉だと思います。
マスケラというのは、イタリア語で仮面のことで、声楽では顔面の上半分くらいのことを指します。
この仮面の部分、つまり顔面の上半分の共鳴(正確には鼻腔周辺の共鳴)を生かせると更に吹きやすく、自由が効くようになってきます。
音が前に飛ぶようになり、響きに芯が生まれます。
マスケラに共鳴を集める感覚をつかむのはなかなか難しいのですが、
教員時代に合唱指導の勉強をしているなかで、とても即効性のある練習を教えていただきました。
2.マスケラに共鳴を集める練習法
①音の響きを三角形でイメージする。
・額、両口角の3点を頂点とした三角形のイメージ。
②その三角形の形で前方向に音が飛ぶようにイメージしながら発声する。
僕はこの練習をきっかけに驚くほど声が出しやすくなりました。
声に芯ができ明るく響くので、そんなにパワーをかけなくてもスムーズに声が通るようになり、歌うことや大勢の前で喋ることが今まで以上に楽しくなりました。声楽家レベルでできているわけではないと思いますが、ここを使えると使えないとでは大きな違いがあります。
この三角形をイメージすることと、音域の階段を後ろに回すイメージをもつこと。これを子供たちにも伝えたいと思い授業ではいろいろと伝え方を工夫して、結局それを一言で、
「ぐるっと回して額からドーンだ!」
と…
今思えばわけわかんない説明をしてましたが、一緒に歌えば伝わります!笑
(先生すげー!って真似するのでなんとなくできる生徒が増えてきます笑)
また「頬骨から上を響かせなさい」とも口癖のように言ってました。どれくらい伝わってたかな〜。
別の中学校の声楽が専門の先生は魔貫光殺砲だせ!って指導してたそうです笑
まあ、一緒にやらなきゃ伝わらないですね!笑
加えて、どうやら呼吸がうまくいっていることがマスケラを使える条件として必要なようです。
やはり順番が大切ですね!
3.マスケラの感覚を楽器演奏に生かす。
僕は自分の演奏動画を見て、「ぐるっと回して額からドーン」が楽器ではできていないことに気づき、試してみたところ劇的に吹きやすくなりました。
響きの意識が後ろに偏っていたようです。
音域の階段は後ろにぐるりとありつつ、響きは常にマスケラに集まって飛んでいく。
こんな感じで吹けるとアンブシュアの負担も軽くなります。


-177x104.jpeg)
-1.png)
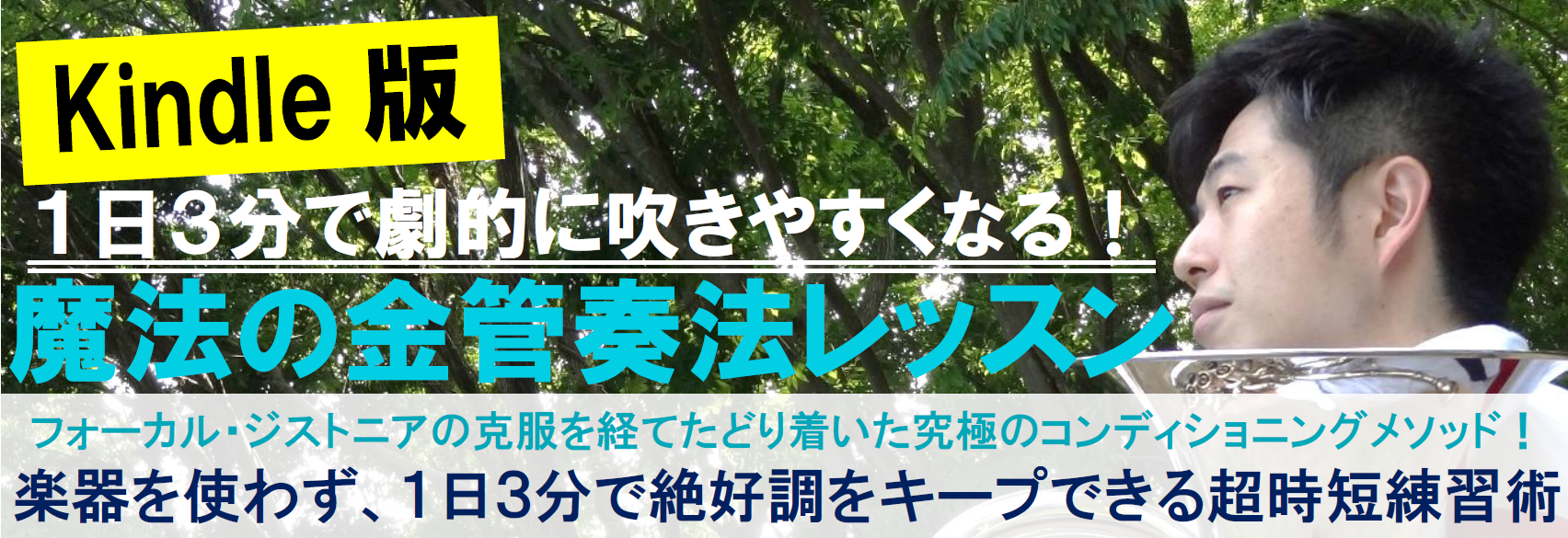
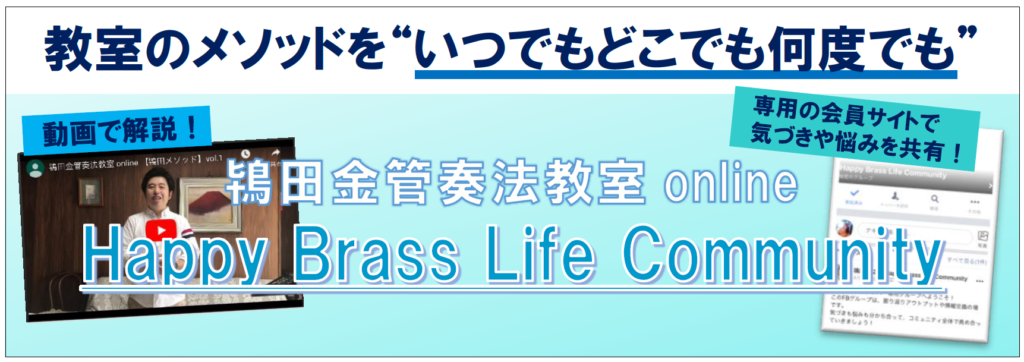
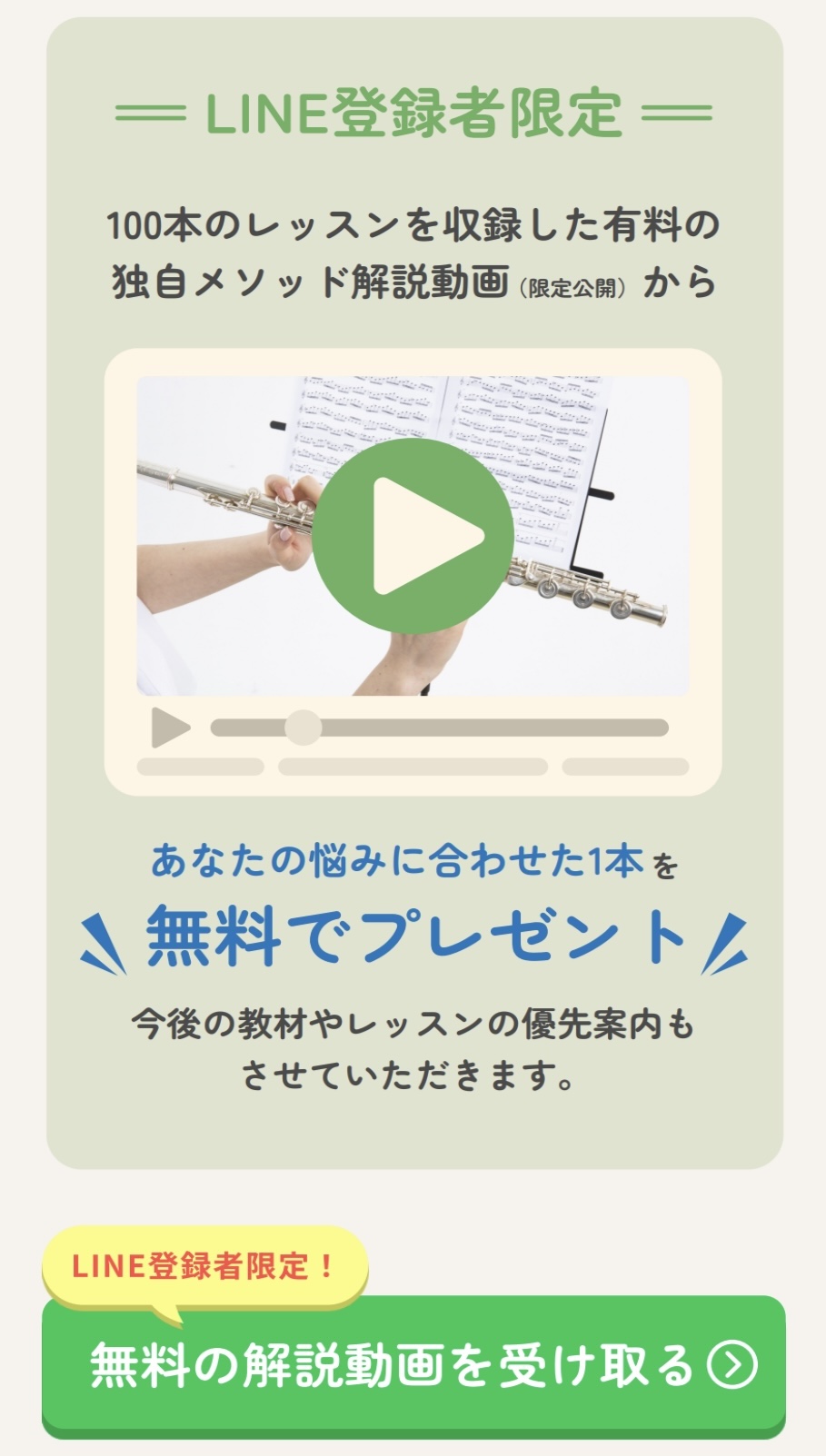
-181x181.jpeg)