.jpeg)
呼吸法には実に様々な理論や流派があり、考え始めると何を選んだら良いのかわからなくなり逆に混乱してしまうような事もあります。
ですが、ここで考えたいのは“何のための呼吸法なのか”ということ。
ヨガや健康法や武術のための呼吸が参考になることももちろんありますが、僕たちに一番必要なのは“楽器を自由に演奏するための呼吸の理解”です。
本来呼吸の仕組みはとてもシンプルなものですが、演奏上の不都合を全て呼吸のせいにしてしまうと、その理解はどんどん複雑化してしまいます。
順番に整えて演奏しやすい体の使い方を思い出すことで自由な呼吸を取り戻す、というような考え方の方がむしろ理にかなっていると思います。呼吸法で管楽器演奏の全てを解決することはできません。発音の前のブレスやフレーズのあいだの短いブレスが上手くいかないのは、呼吸法のせいというよりはそのほかの要因とのバランスが上手く取れていないことが原因です。ですので、順番に整えることで自然と解決します。
前置きが長くなりましたが、今回は呼吸の仕組みだけにフォーカスしてシンプルに理解していきたいと思います。
☆息を吸う動き☆
①横隔膜が下がる
②肋骨が外に向かって拡がる
☆息を吐く動き☆
①肋骨が元の位置に戻る
②腹筋働きで横隔膜が元の位置に戻る
これだけです。
他にも呼吸に関わる筋肉はたくさんありますが、それは、
”求める音楽表現に応じて自然に反応してくれるもの”
です。
普段の呼吸の練習では、上記2つの動きのみ意識してみると頭の中がすっきりして、音楽表現により集中できるようになると思います。
まずは意識化して練習することが大切ですが、慣れたらもう意識の外に出してしまって音楽表現に意識をフォーカスできるようにもっていきたいものですね。
そのことが音楽への集中力にもつながります。

-177x104.jpeg)


-1.png)
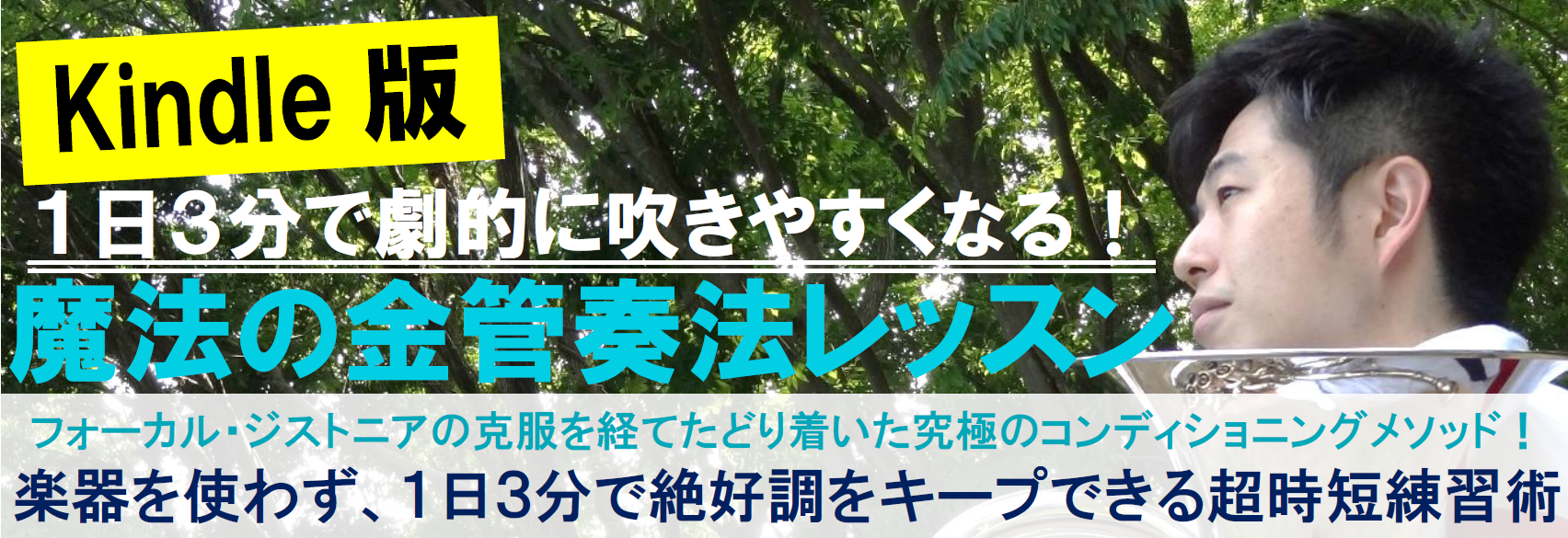
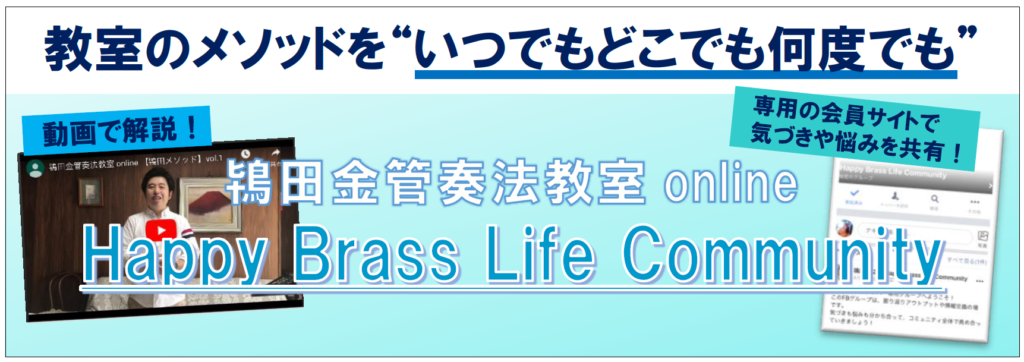
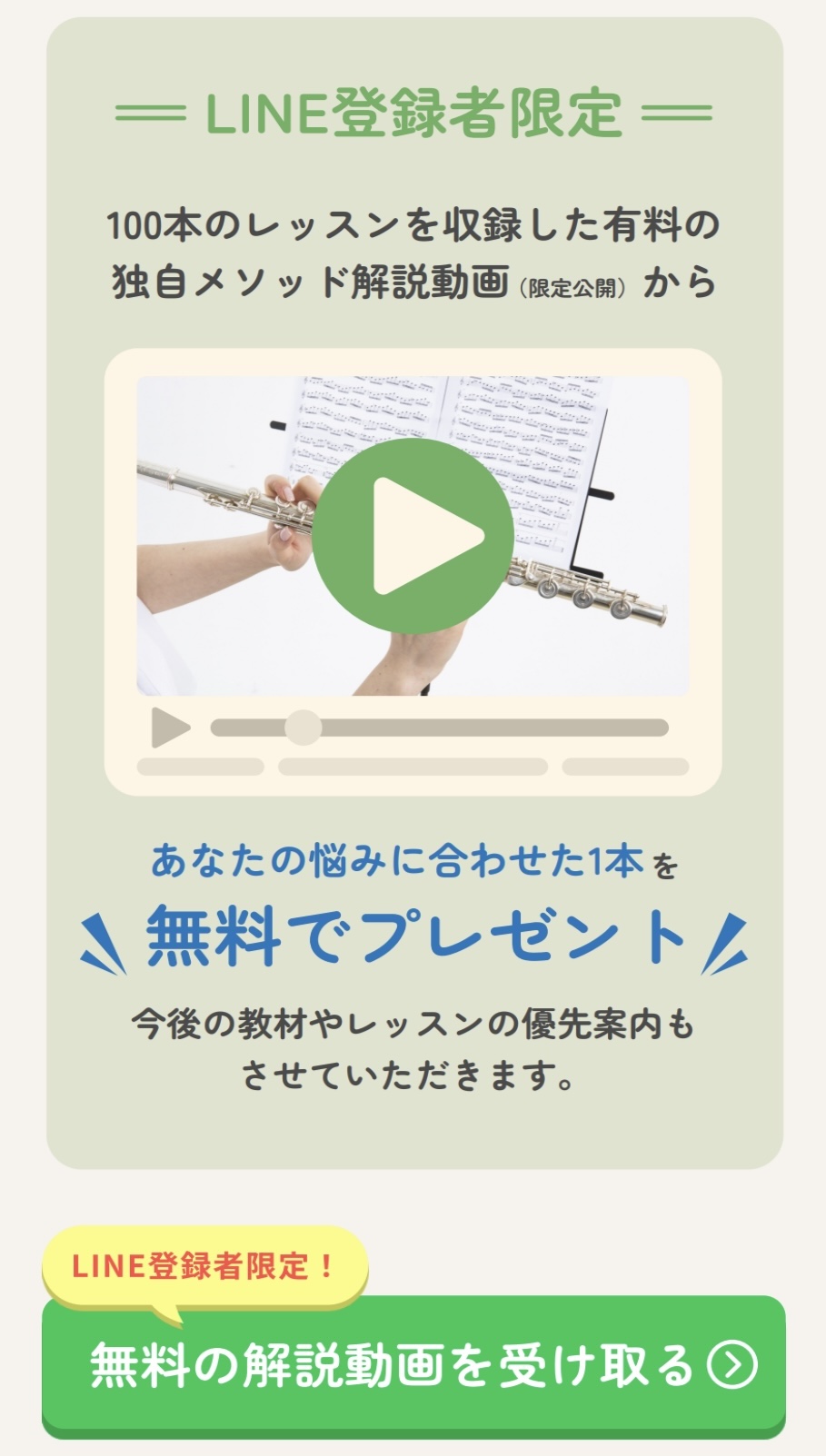
-181x181.jpeg)
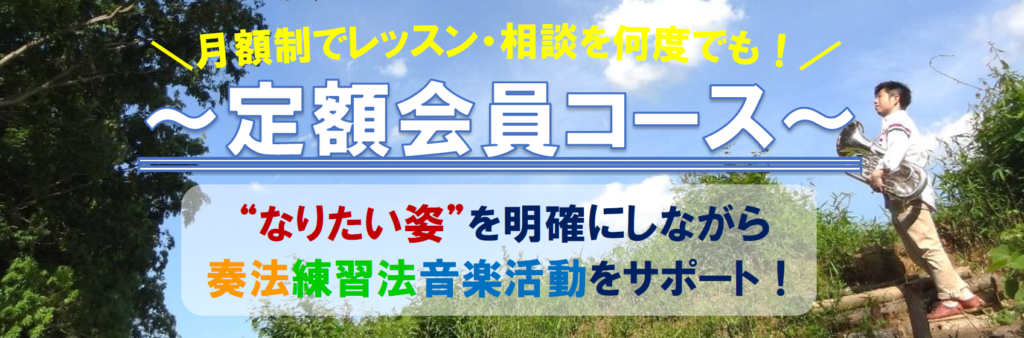

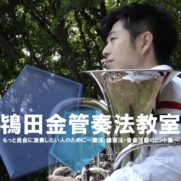



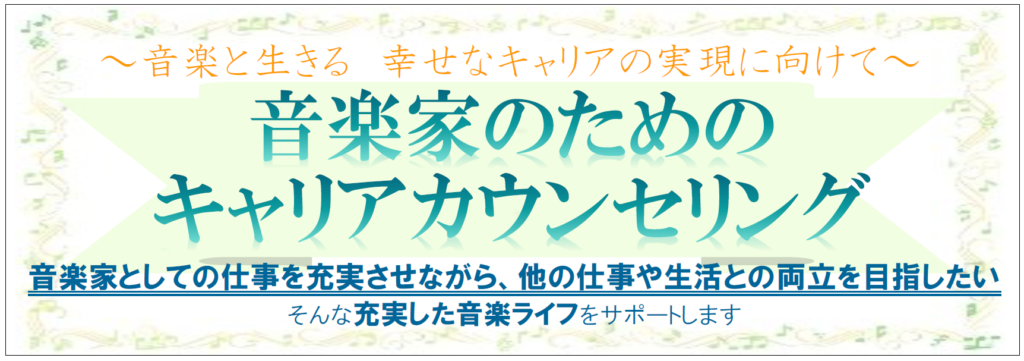
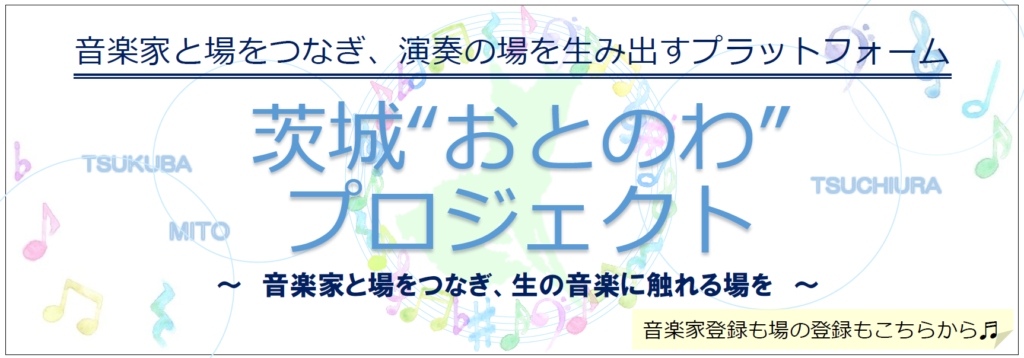
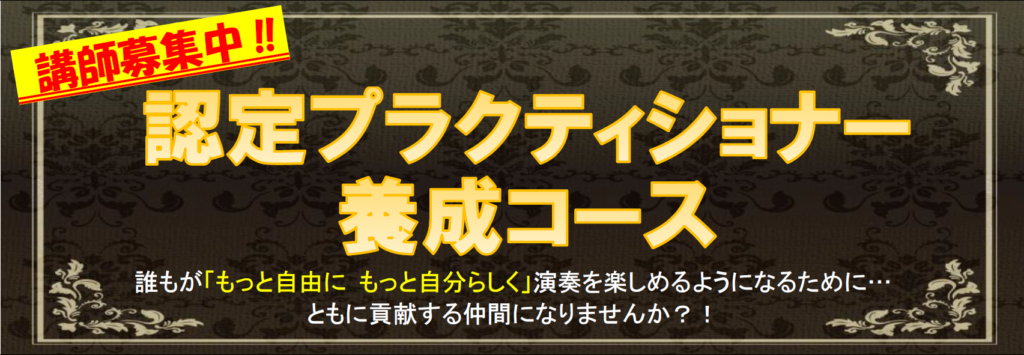

この記事へのコメントはありません。