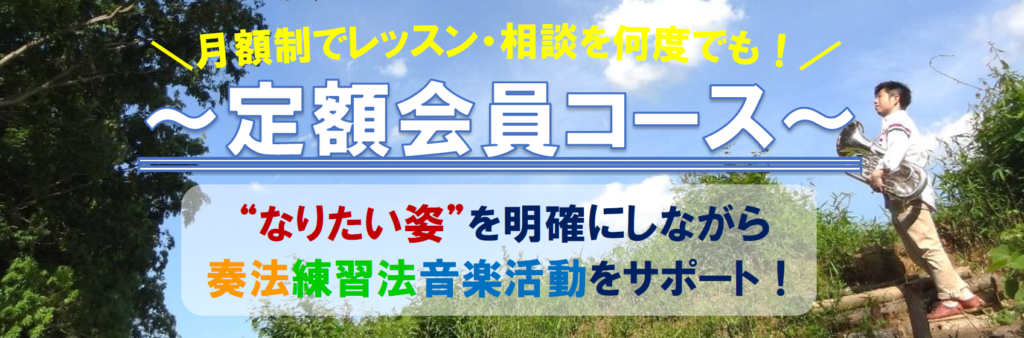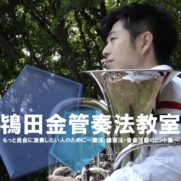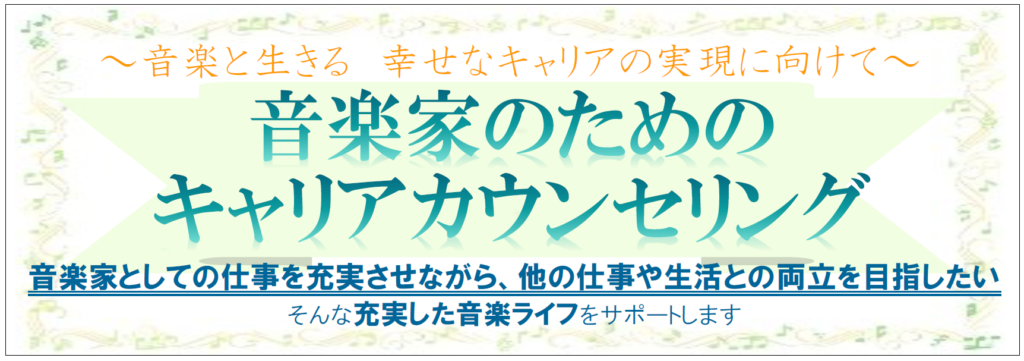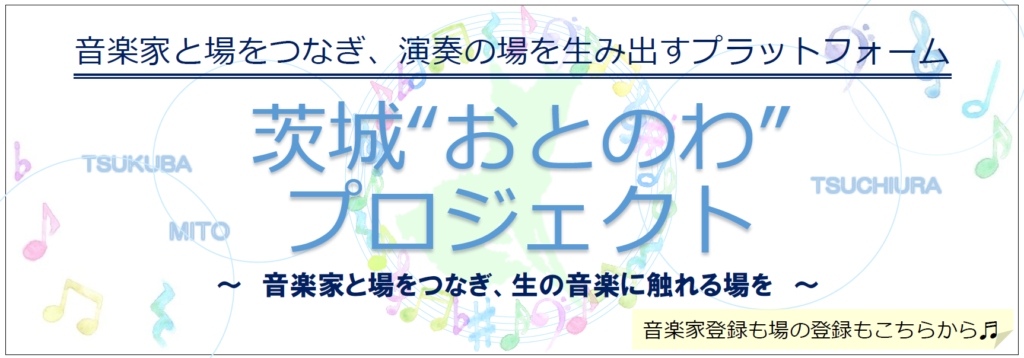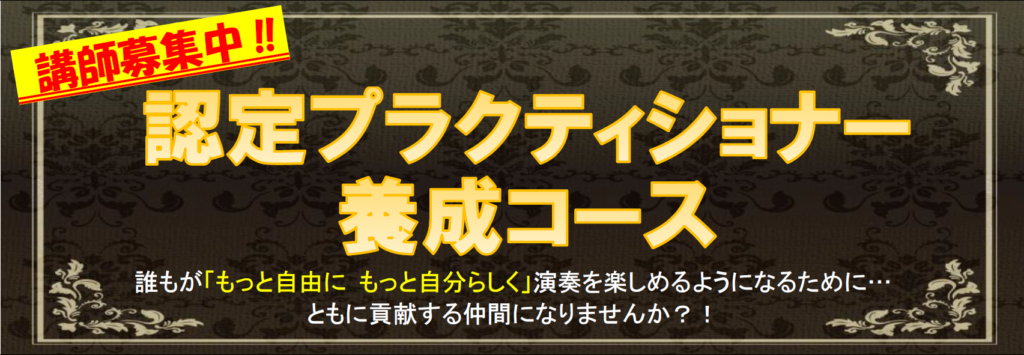.jpeg)
大学院時代、「音の聞き方で音色や演奏が変わる」という趣旨の講習会がありました。
その講習会ではピアノと声楽がメインでしたが、鳴っている音を奏者がどう聞くかで演奏表現や音の響き方が変化する。そのことが体感的にもわかるような驚きの内容でした。
1.金管楽器でも同様
当時の僕は、
録音を聞いたり周りの人に意見を求めたりした時に、「あ、この音がいいな」と思う音は、吹いている実感としては「詰まった音」に感じていました。
逆に、吹いていて気持ちよく柔らかく響いているように感じる時に録音したり意見を求めると、なんとも安定感がなくふわふわした響きになっていたようでした。
2.このパラドックスを超えるには…
おそらく聞いている”場所”が鍵を握っています。
楽器を演奏するとき、どうしても唇のところに意識が行きがちです。
唇の振動に意識が向きすぎていると唇で意識が止まってしまう。
その結果、
唇の振動が楽になっている時には気持ちよく吹けているように錯覚する。
しかし、音は不安定でふわっとしている。
唇の振動が詰まっているような感じがするときにはうまく響いていないと感じる。
しかし、空間に響いている音には安定感がある。
どちらにせよ、どちらも本質的ではありません。
感覚がこうだからいい音が出ているはず、ということではなくて、
“どれだけ空間の音を聞けるか”
“響いているその音をコントロールできるか”
空間に響いている音に意識を向けること、空間の音を耳でとらえることが大切なのだろうと思います。
体に振動が返ってくる以上、純粋に空間の音を聞くのは難しいことであるのは間違いないが、その意識の切り替えで表現は劇的に変わる。
特に注意が必要なのが、消音用のミュートをつけて練習するとき。
空間の音なんてないので、ついつい唇の感覚に頼りすぎてしまう。
触覚的な感覚よりも、聴覚をしっかり生かして演奏を作り上げていく方が良さそうです。
消音ミュートを使うときには、空間に響く音を”イメージする”工夫が必要です。
3.奏法研究のステージと演奏表現のステージでは意識の在り方が全く違う。
音の聴き方、響きのイメージの仕方。
どうやらここを乗り越えると新しいステージが見えてきそうです。
音を生み出すステージから、
空間に音楽を描くステージへ。
奏法を作るための練習ではなく、
音楽を描くための練習へ。
唇に意識が集中するのは、安全にコントロールしたいから。
その根底にあるのは不安や不信。
そのさらに奥にあるのは、不完全さへの不寛容かもしれません。
純粋に音楽表現に集中するには、
“音が出るか出ないか”その不安や不信を手放すことが必要なのかもしれません。
完璧かつ安全に演奏することよりも、
音や音楽を空間に描く勇気をもつ。
もっとピュアに、音楽の中を漂うように、音楽を空間に描くように演奏する。
奏法に囚われている限り奏法の悩みは増え続ける。
音楽表現に集中する事で奏法の悩みは消えてゆく。
「音楽を空間に描くように音を出そう。」
もちろん奏法の基礎を整えた上で。

-177x104.jpeg)


-1.png)
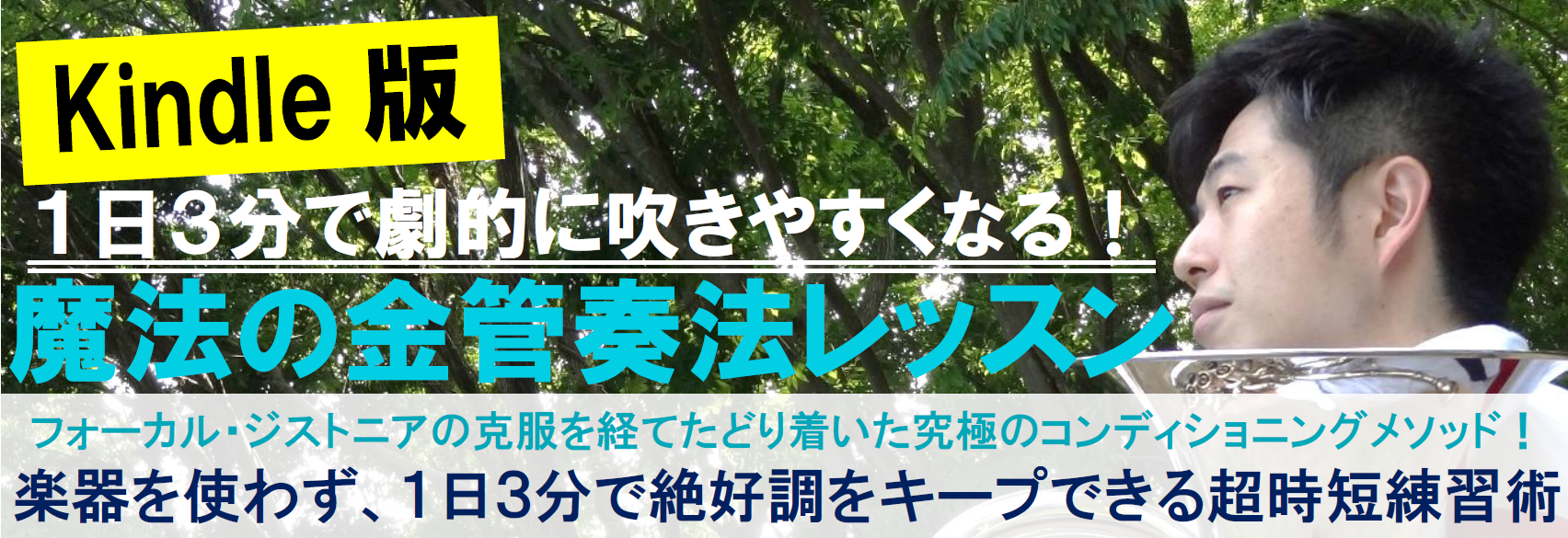
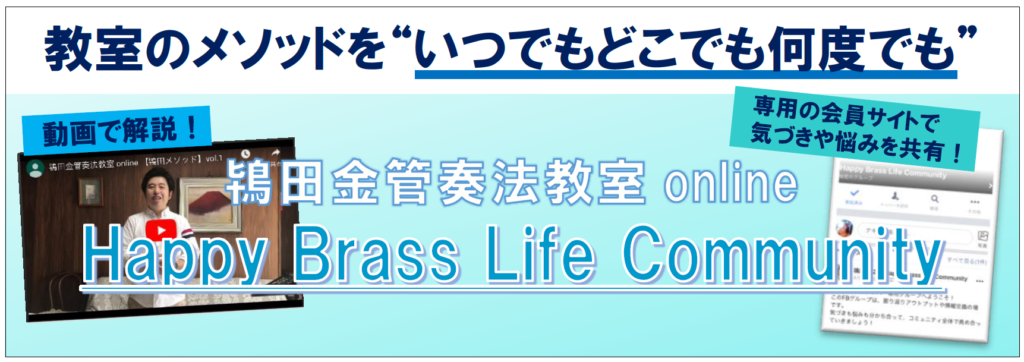
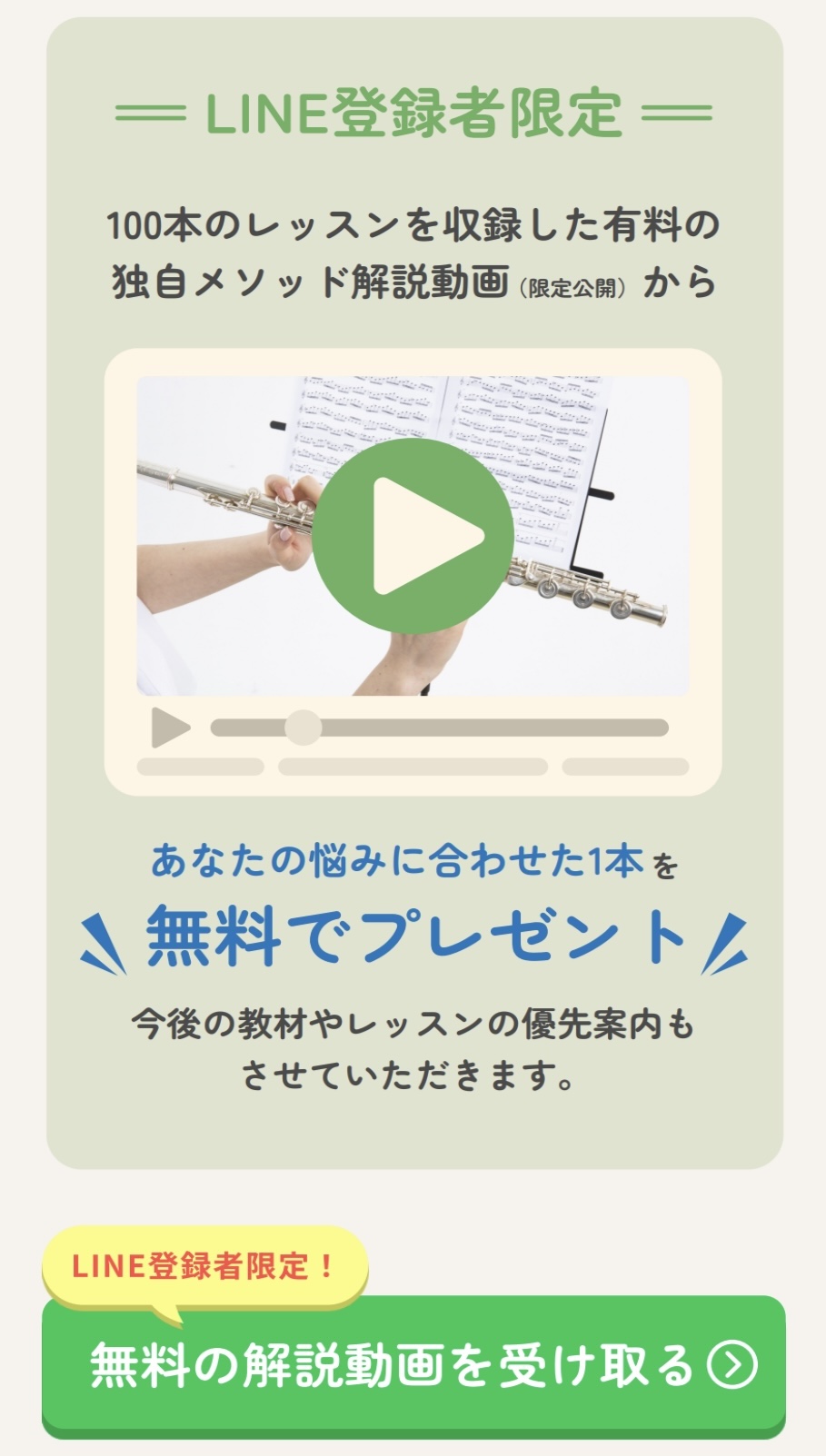
-181x181.jpeg)