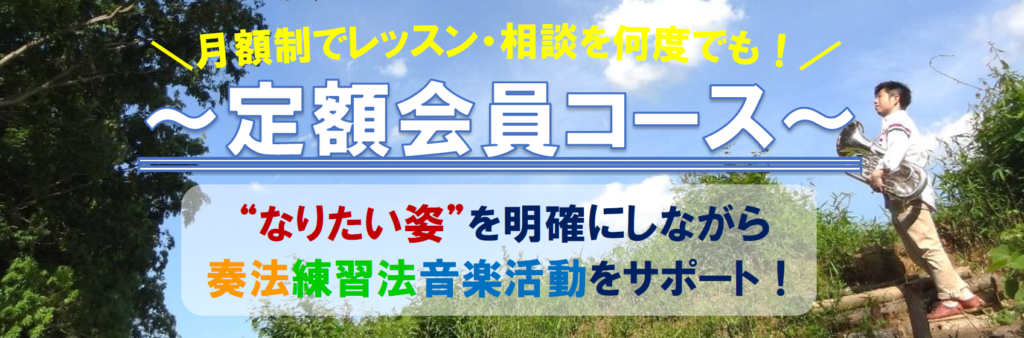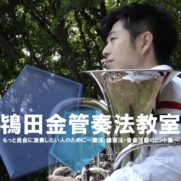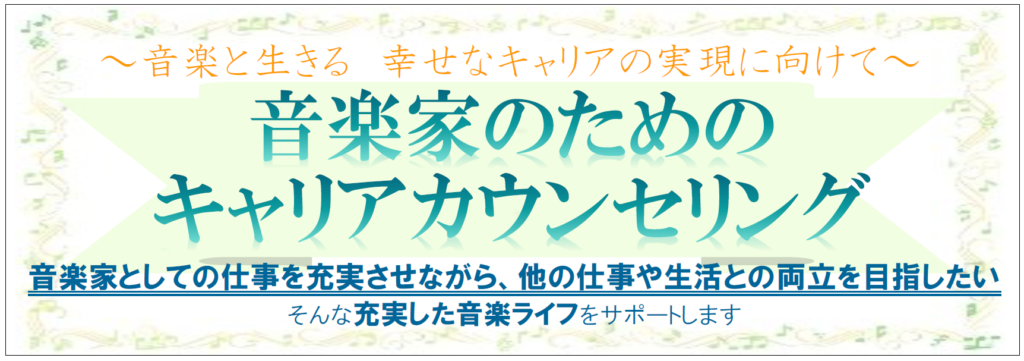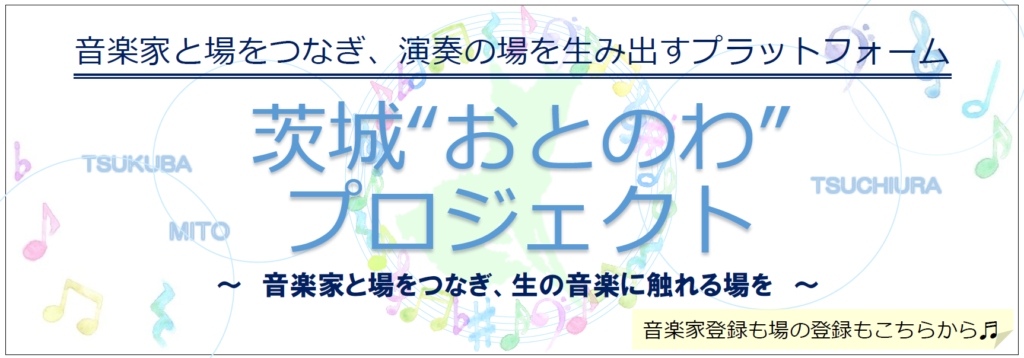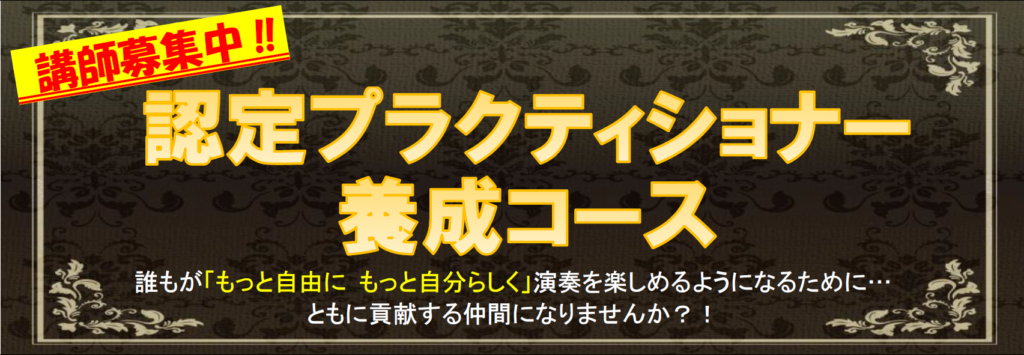.jpeg)
前回は「歌えれば吹ける」理由を2つあげながら、楽譜をドレミで言える・歌えるようにすることのメリットについてお話しました。
・頭の中に設計図ができること。
・声の響きと楽器の響きのリンク
この2点、大切にしていくことで大きな時短になります。
ただ、楽器を吹くときにも「ドレミ」を言っていると口の中の形が安定しないので、当然うまくいきませんよね。
ということで、今回は
④息の流れとタンギングで歌えるようにしておく
〜息の流れを音楽に!〜
と題してお送りします。
1.口の中の形、選ぶ母音
前のシリーズでお話しした通り、楽器を吹くときにどんな母音で吹いているか(あいうえおのどれなのか)によって、アンブシュアの形がほぼ決まります。 僕は「う」がおススメです^_^
ということで、ここに「子音」をつけてみましょう。
選ぶ子音は“ t ”
すると、 「tu」 になりますね!
『声を出さず「tu」で、息の流れでその曲を演奏できるようにしておく。』
ここまでできれば、ほぼ譜読みはできたと言っていいでしょう。
2.スムーズに楽器とリンクさせるために
今回のシリーズコンセプトは「楽器を持つ前に、その曲を吹ける体の準備を体に覚えさせておく」ということでした。
「tu」と一言で言っても、
おそらく10人10色の「tu」があるんじゃないかと思います。
「tsu」になってる人、
「thu」になってる人、
「tho」になってる人、
本当にいろんなタイプがあるんじゃないかなと思います。
楽器を持たずに練習するときは、いかに楽器を吹くときと同じ状態にできるかが勝負です。
楽器を吹く時の、
・潤沢に息が流れる「tu」
・発声のバランスを生かした「tu」
この状態を作れるとスムーズに楽器とリンクします。
3.まとめ
今回は、④「息の流れとタンギングで歌えるようにする」このことのメリットと練習の仕方をお伝えしました。
良い状態で楽器を吹けている時と同じ状態を作って練習することで、スムーズに楽器とリンクさせることができます。
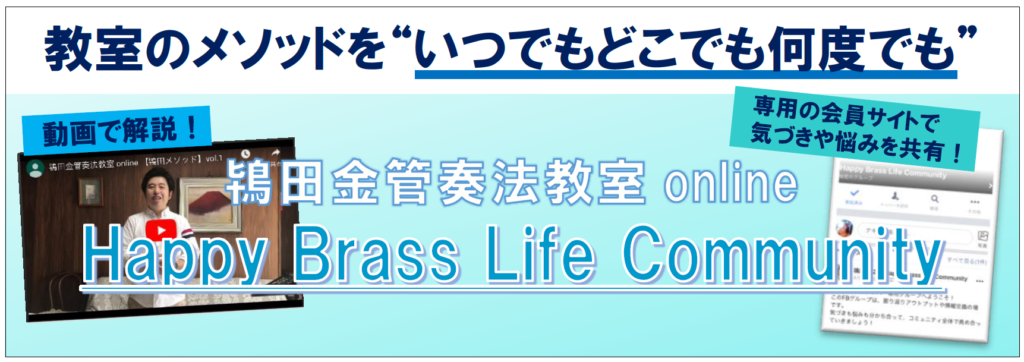

-177x104.jpeg)
-177x104.jpg)

-1.png)
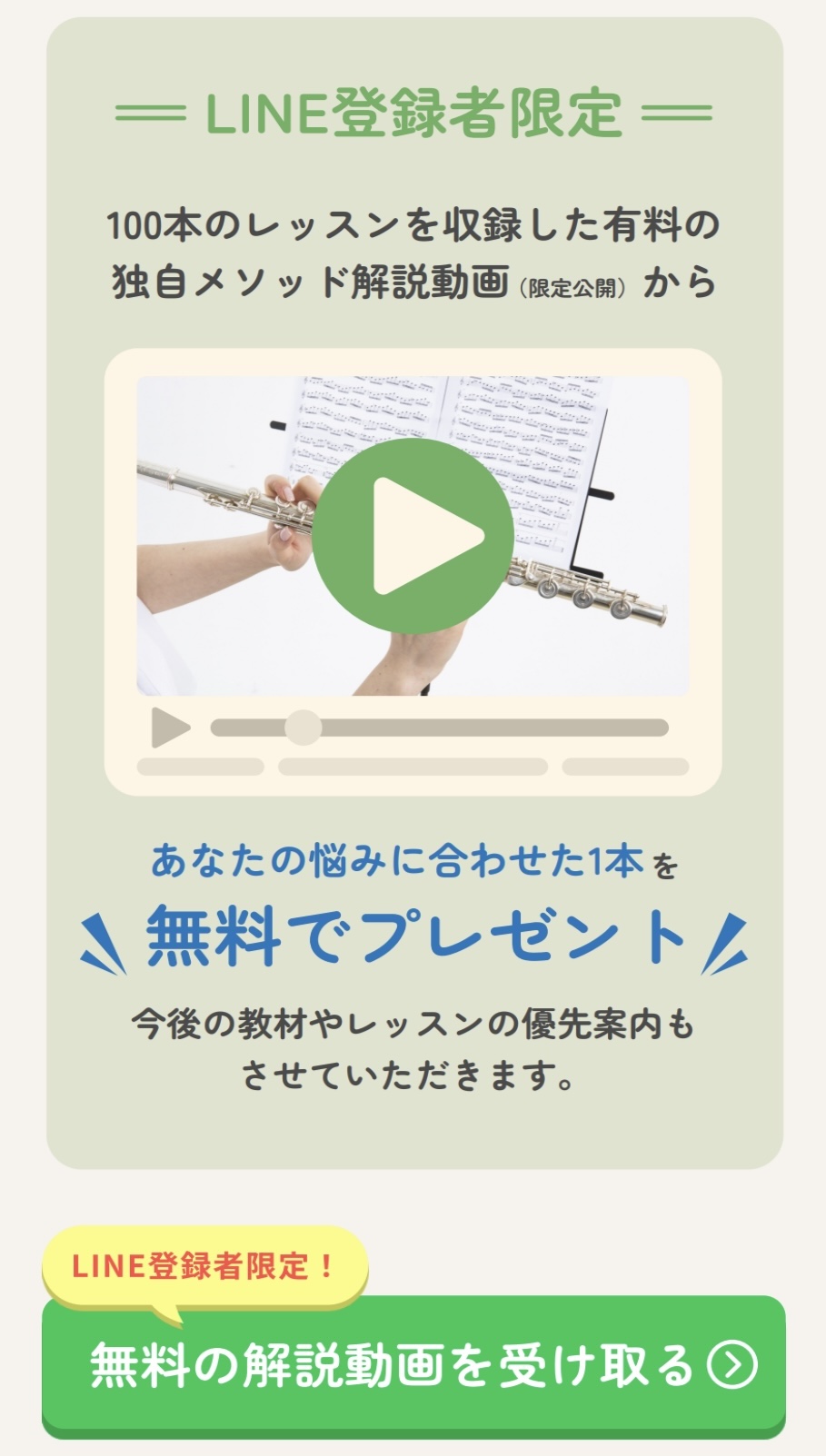
-181x181.jpeg)