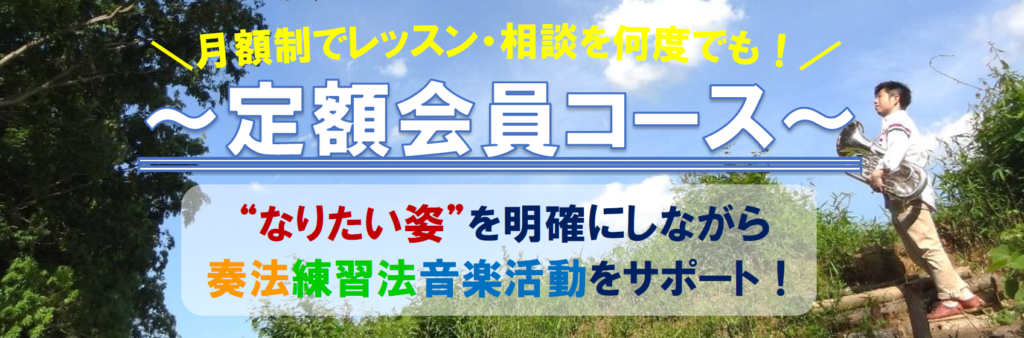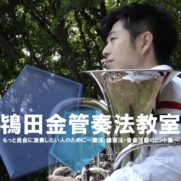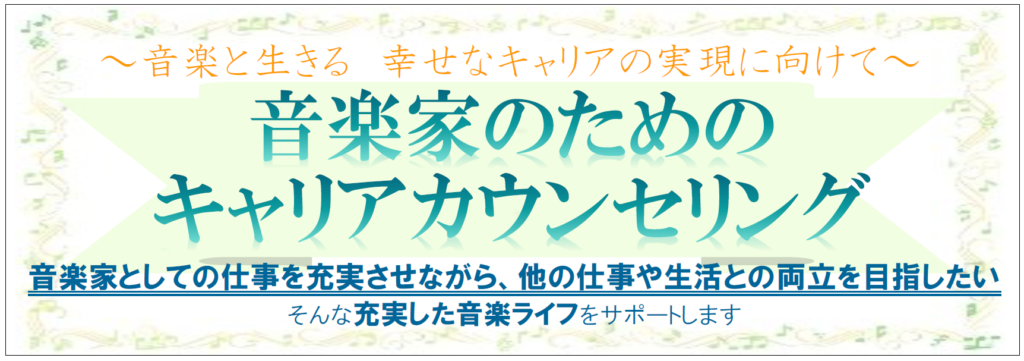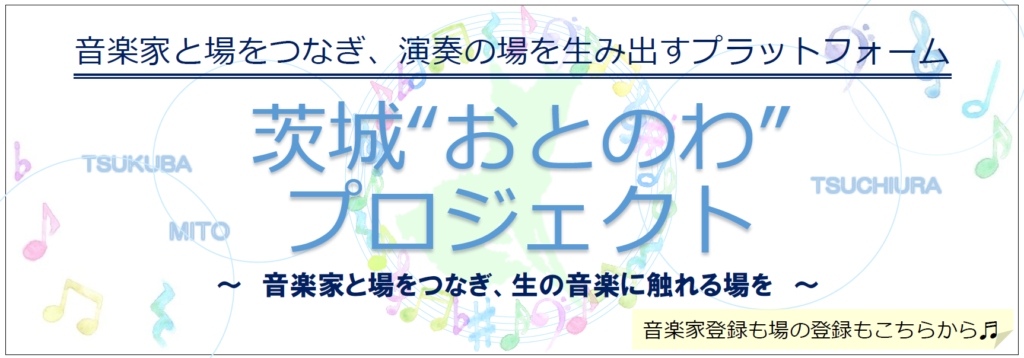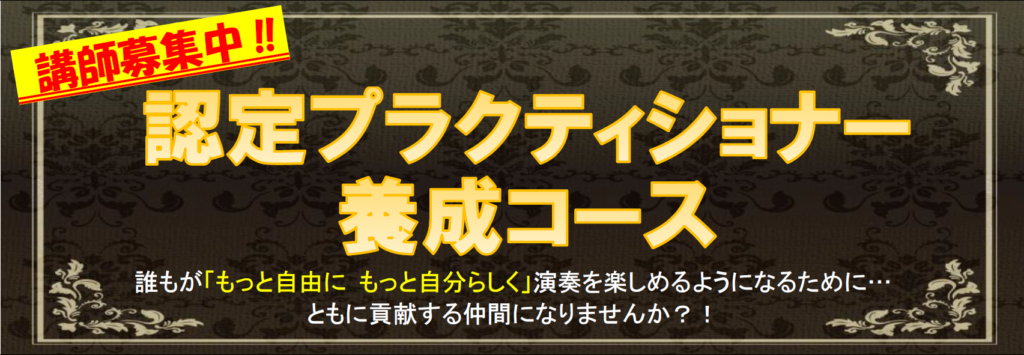.jpeg)
前回は②「楽譜をドレミで言えるようにしておく」というテーマで、口で言えるようにするだけでも頭の中に設計図ができて、その曲を吹くための大切な準備になるというお話をしました。
では、今回は少し進めて”歌えるようにする”ということについてお話します。
ドレミでいうだけならまだしも、そこに音程をつけて歌うというのは、慣れていない方にとっては結構難しいものだったりします。
1.「歌えれば吹ける」理由その2
前回は、口で言えるようになることで設計図ができることが「歌えれば吹ける」理由の1つということをお伝えしました。
今日はもう一つの理由。
前シリーズのvol.3で「声の響きを楽器の響かせ方に生かす」という回がありました。 このことで驚くほど吹きやすくなることがわかったと思います。
ということは、 楽譜を歌うことができると、その響かせ方を曲に生かすことができるのです!
これが「歌えれば吹ける」2つ目の理由です。
3.地声、歌声を簡単に使い分ける方法
僕は歌声で吹ける方が楽器は吹きやすくなると思っています。
なので、今回は簡単に地声と歌声を使い分ける方法をお伝えしたいと思います^_^
①口を思いっきり横に引くように開いて「あー」と言ってみる。
②口を思いっきり真ん中に寄せて「あー」と言ってみる。
…やってみた方はもうおわかりですね。
たったこれだけのことで地声と歌声を切り替えられます。
どちらが駄目と言いたいわけではありません。
使い分けるのは簡単です。
これがそのまま楽器の音色やアンブシュアに直結していくわけですね!
4.まとめ
ということで、今回は楽譜をドレミで歌えるようにするメリットについてお話しました。
・声の響かせ方を曲の中でも生かせる。
・声の響きは音色やアンブシュアに直結する。
このような理由から、 ③「楽譜をドレミで歌えるようにしておく」 ことが大切だと考えています。
また、普段楽器を吹くときから頭の中でドレミで歌いながら吹いていると、この練習が生かしやすいと思います。
ただし、ドレミで歌っている時の口の中の形の変化が楽器でもそのままだと吹けませんよね。当たり前ですね…笑
ということで、②③楽譜をドレミで言える・歌えるようにしたあとで、 それを
④「息の流れで表現する」
というステップが大切になります。
☆kindle版『3分で変わる!魔法のレッスン』
70ページにぎゅっと凝縮♬(実践動画付き!)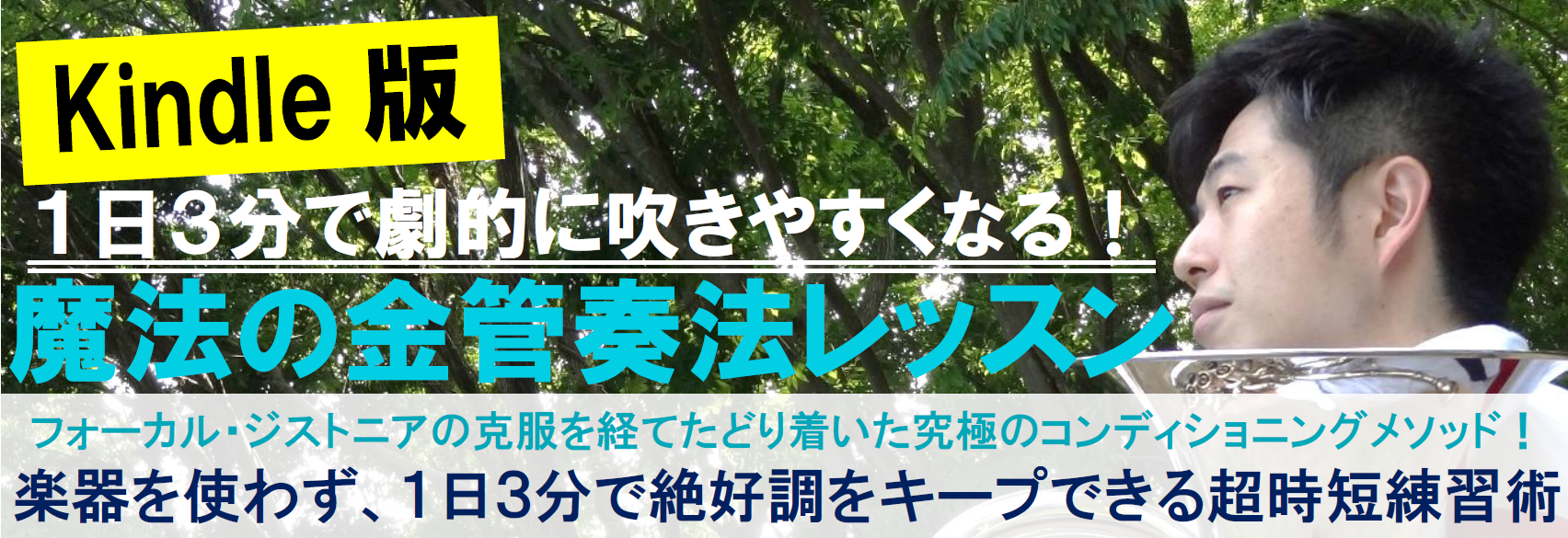

-177x104.jpeg)



-177x104.jpg)
-1.png)
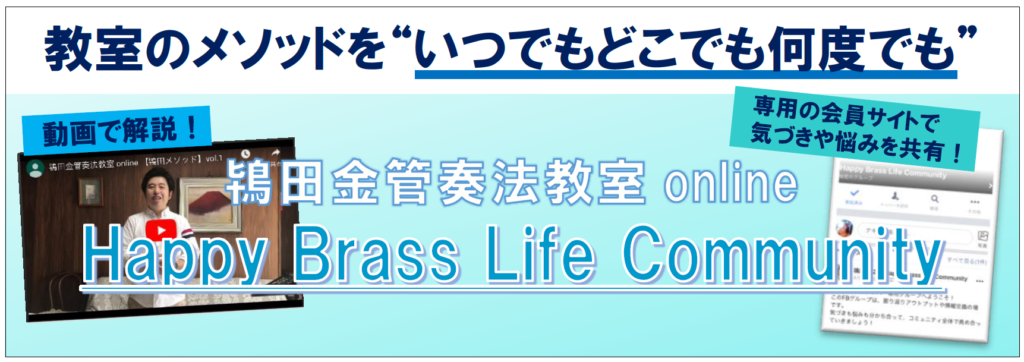
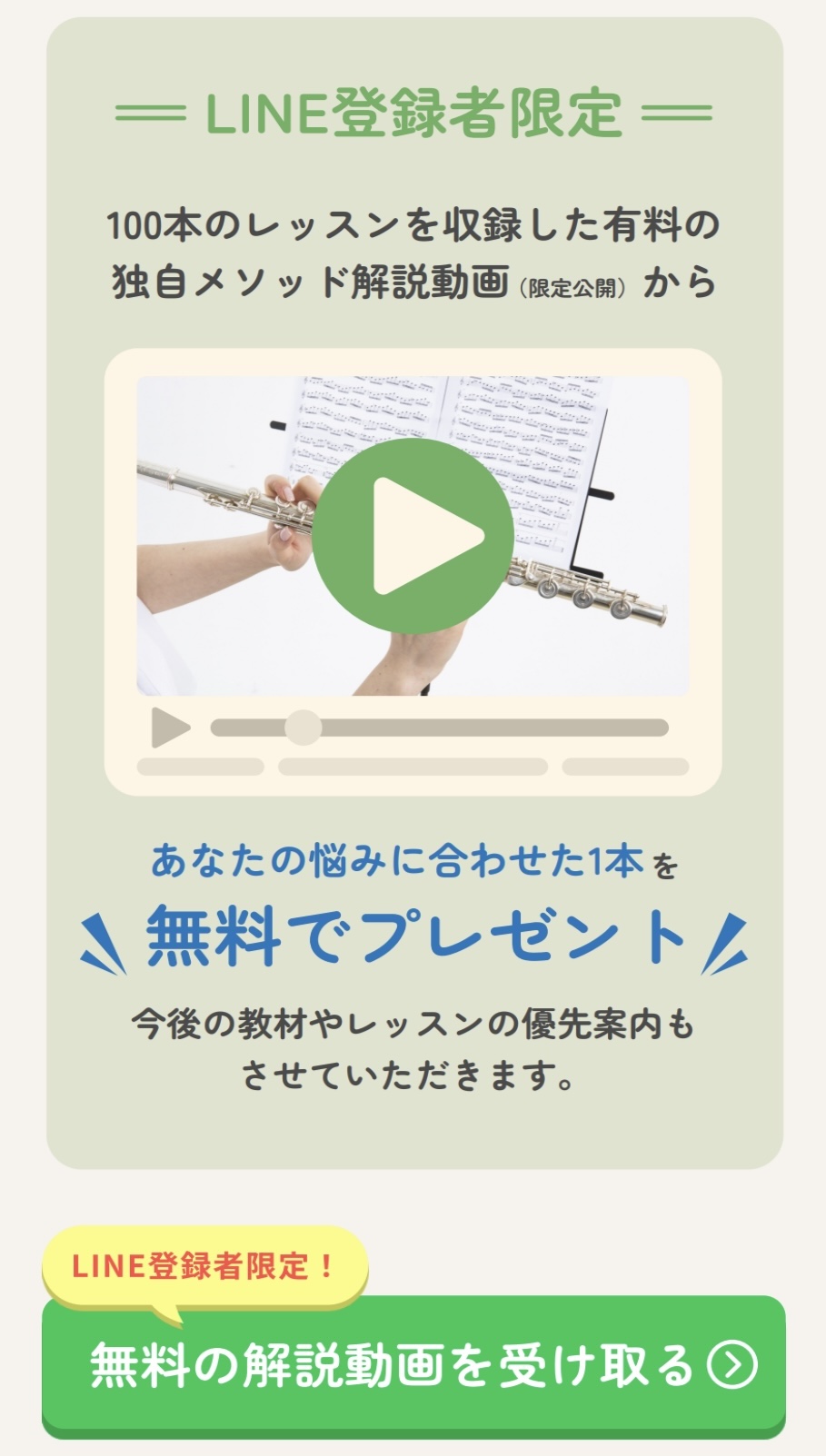
-181x181.jpeg)